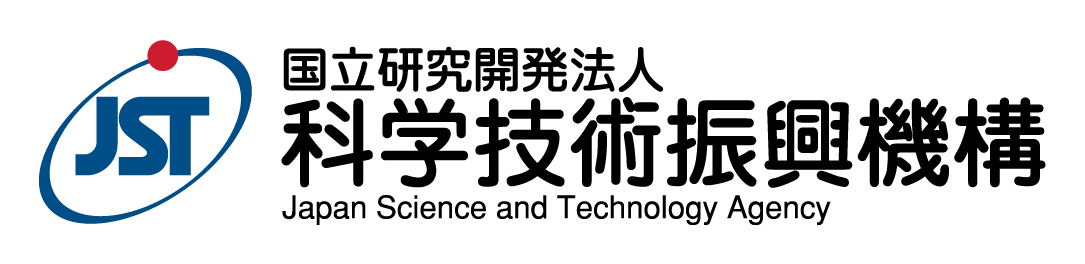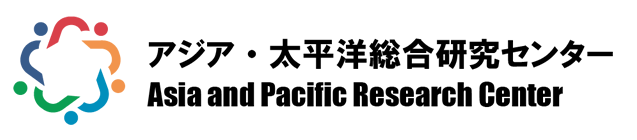日 時: 2021年9月13日(月) 15:00~16:30 日本時間
開催方法: WEBセミナー(Zoom利用)
言 語: 日本語
講 師: 伊藤 亜聖 氏
東京大学社会科学研究所 准教授

伊藤 亜聖(いとう あせい)氏
東京大学社会科学研究所 准教授
略歴
東京大学社会科学研究所准教授。専門は中国経済。
著書・共著に『現代中国の産業集積「世界の工場」とボトムアップ型経済発展』(名古屋大学出版会、2015年。大平正芳記念賞、清成忠男賞受賞)、『中国ドローン産業発展報告2017』(東京大学社会科学研究所、2017年)、『現代アジア経済論』(有斐閣、2018年)、『デジタル化する新興国 先進国を超えるか、監視社会の到来か』(中公新書、2020年)。
第4回アジア・太平洋研究会リポート
「デジタル化した新興国 日本は『課題先進国』の経験提供に活路―東大・伊藤准教授講演」
9月13日開催のアジア・太平洋研究会で、東京大学社会科学研究所の伊藤亜聖准教授が「デジタル化する新興国~共創パートナーとしての日本の可能性~」と題して講演した。2020年に出版した伊藤氏の著書『デジタル化する新興国 先進国を超えるか、監視社会の到来か』は第22回 読売・吉野作造賞を受賞。講演ではデジタルによって変化する新興国の動静をポジティブな面とネガティブな面から概説した。そのうえで、日本のビジネスチャンスについて提言した。
なぜ中国研究者が新興国を扱ったのか
伊藤氏は講演で、デジタル化という言葉の定義について、「世界銀行の報告書の三つの変化が重要だと思っている。それは情報格差あるいは非対称性の解消、自動化技術の普及、そしてプラットフォーム企業の台頭だ。さらに、物質的には情報通信端末の普及が前提となっている」と指摘した。
伊藤氏の専門は中国経済だが、なぜ中国研究者がデジタルや新興国をテーマに扱ったかについて次のように振り返った。
「中国企業を追いかけていく過程で、一帯一路構想もあり中国企業の海外展開が盛り上がってきた。中国経済、中国企業を研究するために、中国の国境を越えて、カザフスタンや東南アジア諸国、それから南アジア、インド、そしてアフリカ、エチオピア等々にまで中国企業を追いかけていくという経験をした。その中で、中国のアリババ、テンセントに代表されるデジタル企業の研究をしていたが、新興国は広い意味でデジタル化が進んでいるのではという着想・直感を強く持ち、『デジタル化する新興国』というタイトルの本を刊行した」
デジタル化の可能性と脆弱性
伊藤氏は「私の書籍は小さな本だが、大きく二つのねらいがある。一つは、新興工業国論を念頭においてデジタル新興国論の提案、二つ目は、新興国がデジタル化する時代を想定した場合の日本の役割である」といい、書籍で示した問題意識の一部を講演で紹介した。
その中で、デジタル化が本格化する前の1995年から、2005年、2015年と10年刻みで、情報端末(固定電話、インターネット、携帯電話)の普及の推移を低所得国、中所得国、高所得国に分けて次のように比較し、分析した。
- 1995年 Windows95が発表された年で、インターネットはダイヤルアップで接続していた。電話はまだ固定電話が中心で、固定電話の普及は低・中所得国は進んでおらず、高所得国に限られていた。
- 2005年 高所得国中心に携帯電話が普及し始めた。それでも低・中所得国での固定電話、携帯電話やインターネットの普及は限定的だ。全体で見てもこういった情報通信機器の普及は低い水準にとどまっていた。
- 2015年 高所得国のみならず、中所得国を中心に携帯電話中心とした情報通信端末が普及した。低所得国においても携帯電話の契約件数はかなり増加してきた。
これらの分析のうち、とりわけ2015年のデータは、低所得国では固定電話のインフラが整備される前に携帯電話が急速に普及していた事例などを示した。伊藤氏は2018年、低所得国に位置づけられるミャンマーを訪問した際にそのことを如実に物語る次のようなシーンに遭遇した。
「私が一番印象的だったのはミャンマーの地方都市にある縫製工場を訪問した時だった。工場でミシンを踏んで作業をしている女性従業員たちが休み時間に、座り込んで携帯電話見ていた。何をやっているのかなと思って見せてもらったら、女性たちは動画を見ていた。そういったデジタルライフをごく普通に送っていた」
伊藤氏はそのほかの発展途上国や新興国を訪問する機会を得た。「ミャンマーでもそうだったが、エチオピアにおいてもスマホショップが並び、格安ショップが中心にそういった端末を購買する層が出てきた」と語る。
それぞれの国の実情を掛け算
インドではその先を行き、グローバルなデジタル化が実現しつつある。伊藤氏は2019年夏、インドのグルガオンというデリー郊外を訪れた際に次のような経験をしたという。
「インドのグルガオンに行く機会があり、現地でスマートフォンのウーバーのアプリを立ち上げた。翌朝また、ウーバーを立ち上げると、上の欄には四輪車の表示が出ており手配が可能と書かれていた。私が驚いたのはその下の欄に三輪バイク、二輪バイクが出ていて、それらもウーバーで呼べることである。実際に呼んでみると三輪バイクが来て移動できた」

ウーバーでやってきた三輪バイク
(出所:インド・グルガオンにて伊藤氏撮影。)
「このウーバーのアプリはグローバルで使えるアプリだった。私は日本でアプリをダウンロードしたが、アプリはインドでそのまま立ち上がって日本語が表示されていた。デジタル化といわれるモバイルインターネットを使ったシェアリングエコノミーという変化はグローバルな変化といえる。国を分けることなく非常に幅広い地域でシェアリングアプリが台頭する。そのユニバーサルでグローバルなサービスや変化が、最後の最後、現場ではそれぞれの国・地域の産業、特徴、姿などが現実との掛け算になっているということを強く感じた。グローバルなデジタル化という変化とそれぞれの国における実情を掛け算して、非常に面白い様々なデジタル化、私はそれぞれのデジタル化という風に呼んだりもしている。そういった変化がとりわけ新興国では興味深い形で進んでいるのではないか」
「当初はアメリカのホワイトカラーの仕事をインドでアウトソーシングするという話が中心だった。北の先進国のための、南のIT化というような話だった。しかし、今動きつつあるのは新興国の課題を新興国の企業家、企業が解消しようとするもので、南による南のデジタル化である。そこに根本的な変化がある」
デジタル化によるリスク
とはいえ、デジタル化による新興国のリスクもある。
伊藤氏はリスクの一つとして「経済の面では労働市場の問題がおそらく一番重要である。デジタル経済が広がっていくことによって、新しい雇用も生まれるが、とりわけ数の上で多いのはラストワンマイルの配達や、フードデリバリーや宅配郵便といった業務になる。このようなギグ・ワーカーと言われる労働者は正規雇用ではなく、社会保障制度の対象外におかれているケースが多い。私はインフォーマル雇用という言葉を使用している。フォーマルな雇用というのは公的な社会保障の中に含まれているもので、そこに含まれていない外側のものをインフォーマル雇用と線引きをしている。その場合デジタルインフォーマルの部分が増えてしまい、これをどうするのかを考えなくてはならない」と指摘した。
もう一つ、権威主義体制の国家で起きつつあるリスクについて「政治的には特定政権あるいは個人に権限が集中する権威主義体制とデジタル技術というのがある意味で相性がいいので、それによって人々を監視、検閲することが容易になっている事実がある。『幸福な監視国家中国』という書籍を紹介した。自分の情報を提供することによって便利になるということをやっている視点からすると、決して我々と無関係な論点ではないという議論だ。
共創パートナー日本の役割
伊藤氏は、日本が共創パートナーとして新興国に働きかけることについて自説を披露。まずポジティブな面では、「デジタル化が新興国の可能性を広げるために日本企業も協力していく、そして願わくは、それを日本に還流していくことが求められる。インドで普及している生体認証は、日本のNECが技術を提供している。新興国のスタートアップあるいは現地の財閥とのネットワーキングを進めるような動きも出てきた。ビジネスの実証実験の話も進んでおり、戦略投資の話だと、コーポレートベンチャーキャピタルあるいは、より大規模なソフトバンクビジョンファンドという形で新興国の有力新興企業への投資が進んでいる。日本への還流でいうと海外スタートアップ企業に東証に上場してもらおうという取り組みもある」とした。
ネガティブな面として、「新興国がデジタル化してくることによって顕在化してくるリスクにも目配りすることが必要となる」と指摘。日本の役割については「労働市場の問題では、技能の形成ではデジタルリテラシー教育が重要になってくる。日本でもAI(人工知能)人材、データサイエンス人材に関する教育のパッケージやカリキュラムを作っている。もしかしたら海外展開もあり得るかもしれない。それから、海外のサイバーセキュリティへの支援、ファクトチェック機関への支援なども可能だ。日本政府はこういったルール作りにも参画する状況だ」と提言した。
そのうえで、日本企業の海外での取り組みの一つとして、経済産業省が立ち上げたアジアDX(デジタルトランスフォーメーション)プロジェクト(ADX)を挙げた。アジアにおいて日本が、資金、技術、ノウハウ、ネットワークを提供して課題を解決していこうというプロジェクトだ。日・ASEAN(東南アジア諸国連合)、日・インドの二つの枠組みがある。伊藤氏は、「日本企業が東南アジアで事業というと製造業の話を思い浮かべるが、実は介護や農業の割合が大きいのは面白い構成だ」とし、ASEANに日本企業が実証実験に打って出るプロジェクトについて公開情報を基にいくつか紹介した。
大企業、スタートアップ、中小企業の取り組み
伊藤氏は、日本企業の取り組みを紹介したうえで次のように指摘した。
「日本企業のDX海外展開は総量としてはまだまだ不足しているが、潜在力がある。その際に求められるのはまず差別化である。どこと差別化するのかというとグローバルプラットフォーム企業である。プラットフォーム企業ができることをやっても意味がない。一方で地場企業、例えばインドネシアやブルネイ、タイの地場企業ができることをやっても意味がない。一つは日本国内で先行展開済みの業界、用途特化型のソリューションを海外で少し試してみるのが、現状動きつつある話だ。その場合にIoT(モノのインターネット)のソリューションを現場に入れなくてはならないから、現場にどう落とし込んでいくのかという工夫がおそらく求められるだろう」と伊藤氏は語る。
医療なら病院、介護福祉なら施設、中古パーツなら修理工場、漁業なら漁港あるいは漁民。こういった現場にどう浸透していくかは、現地パートとの協力が求められるという。
最後に伊藤氏は「日本が進出している海外の事例をみていくと、介護福祉といった領域がかなり出てきている。共創パートナーとしての日本という時代においても、これまでの強み、例えば『課題先進国』としての日本が蓄積してきたノウハウ、サービスを生かしてくという可能性は十分ある。もちろん、製造業のノウハウも生かせると思うし、これまで日本が蓄積してきた力、ソリューションをデジタルの時代にも生かしていける」と締めくくった。
(文: サイエンスポータルアジアパシフィック 編集長 大家 俊夫)