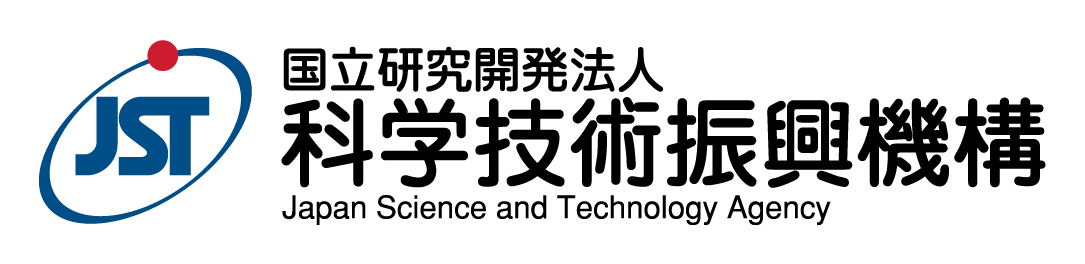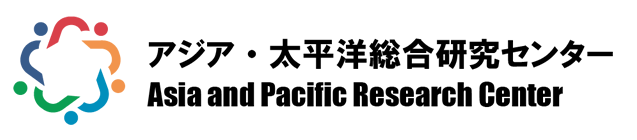ビヨンドコロナのインドとの経済外交「日印連携でグローバル・ゲームに対抗を」
2021年8月6日

松島大輔(まつしま だいすけ):
金沢大学融合研究域 教授・博士(経営学)
<略歴>
1973年金沢市生まれ。東京大学卒、米ハーバード大学大学院修了。通商産業省(現経済産業省)入省後、インド駐在、タイ王国政府顧問を経て、長崎大学教授、タイ工業省顧問、大阪府参与等を歴任。2020年4月より現職。この間、グローバル経済戦略立案や各種国家プロジェクト立ち上げ、日系企業の海外展開を通じた「破壊的イノベーション」支援を数多く手掛け、世界に伍するアントレプレナーの育成プログラムを開発し、後進世代の育成を展開中。
著者はコロナ後の通商秩序や経済的な日本の立ち位置について、かなり深刻に考えている。結論を先取りすれば、米中の経済覇権をめぐるグローバルな角逐のなか、インドこそが日本にとって救世主ではないか、という見立てである。ひと時、環太平洋パートナーシップ(Trans Pacific Partnership :TPP)が国論を二分した時期があった。実はその裏で進行していた通商秩序が、(アジア)地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership:RCEP)である。コロナ禍のグローバルな混乱のなかにあって、2020年11月に「ASEAN+1」と呼ばれる、東南アジア諸国連合(ASEAN)と地域連携を進める15カ国との間でこのRCEPの条約に署名がなされた。そして、日本でも2021年3月28日には参議院本会議で本条約の承認、国会での批准的続きが終わり、署名した15カ国の批准状況によっては、年内にRCEPが発効する予定である。
このRCEPは、2010年という年がターニング・ポイントとなった。それまで、ASEANをハブ(Hub)として、経済連携協定を結んでいた日本をはじめ、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、そして、インドが「ASEAN+1」を拡大させ、東アジアサミット(East Asia Summit:EAS)を進め、このフォーラを通じて経済連携協定を、いわば一つの軸から面的に地域的に拡大させようという動きがみられた。東アジア共同体やアジア太平洋経済協力(APEC)の初期の動きに代表されるように、日本の戦後の経済外交上、アジアに米国をどう位置付けるかについて、アジアでまとまるか、米国も取り込むか、その二つのポジションで絶えず振り子のように動いてきたように思われる。そして、2010年までには、米国との関係性を相対化した連携を模索したが、最終的には米国のみならず、ロシア、さらには欧州なども巻き込む、巨大なEASへ拡大し、拡散していった。当初の「ASEAN+1」の経済連携を前提としたハブ&スポークの地域連携秩序が大きく変貌したのである。このなかで、新たな地域経済連携の枠組みとして検討されたのがこのRCEPであった。つまり、当初はインドも含む、16カ国の体制として構想されたのである。
しかし最終的にはインドはRCEPに参加することはなかった。交渉途中で離脱することを決めたのである。なぜインドがこのRCEPに加盟しなくなったのか。そしてこれによって日本の立場はどうなっていくのか、それがここでの問題意識である。インドがなぜRCEPに加盟しなくなったのか。これについては、いくつか背景があるが、個人的にはインドが、国内で完結した国民経済圏を形成し、それによって域外に対してインディペンデントな貿易構造になっていることが重要な要因となるだろう。表(下記参照)でみるとおり、現下の貿易依存度でみても、インドは現行発足予定の15カ国が連携するRCEP全体の依存度に比べても低い水準にある。インドは「歯磨きからロケットまで」と呼ばれた1990年代の自由化以前の「鎖国」的経済秩序が前提となっている。従って他国との相互依存を高めることも少ないだろう。つまり、裏を返せば、グローバルなサプライチェーンに再編されず、 連携が深化していないということが原因といえるだろう。
| 域内輸出依存度 | 域内輸入依存度 | |
|---|---|---|
| RCEP | 8.4% | 8.9% |
| インド | 2.2% | 5.8% |
出典:IMF:DOT(2020年9月)
ASEANを中核としたアジアの経済連携秩序は、これまで日系企業、特に日系製造業企業の工場進出などを通じた海外直接投資(Foreign Direct Investment:FDI)の海外生産ネットワークを通じて形成されてきた。その核となっていたのは、自動車産業であり、電気電子産業であった。ミネルバの梟(フクロウ)は黄昏に飛翔す-。2000年代から日本が構想してきたアジア経済秩序は、飽くまでこうした日系企業主導の秩序であったことを想起すべきである。何人かの論者が指摘している通り、RCEPが期待してきた日本主導の秩序は、軌道修正を余儀なくされつつある。中国の台頭、特に世界に先駆けてコロナ禍を克服しつつある中国の対外的影響力の強化、ワクチン外交など、「一帯一路」経済圏の実体化について、かつては想像できなかったことである。こうした中国が主導するアジアの経済秩序において、日本は大きなゲームチェンジを迫られることになるだろう。特にデジタルトランスフォーメーション(DX)化の進展と「グリーン・リカバリ―(Green Recovery)」による内燃機関による旧来型自動車産業の駆逐によって、これまでの日系企業の強みは相対的に劣位におかれるだろう。ことは、平成時代を通じて進行した「失われた30年」、電気電子産業の総崩れどころの騒ぎではない。日本産業の死命を制する事態に直面しつつある。何か? 2030年を前後して、世界各国が電気自動車(EV)以外の車の生産や販売を禁止していく。日本自動車産業のプレゼンス、特に雇用全体の1割、製造業付加価値額の2割を紡ぎだしてきた自動車産業が立ち行かなくなる可能性がある。自動車メーカーだけではなく、自動車部品を共有する優良な中堅・中小企業も同様に岐路に立たされることになるだろう。日系企業に残された時間は限りなく少ない。イーロン・マスク(Elon R. Musk)氏率いる米テスラ社(Tesla, Inc.)は、既に2021年中にインドへの工場進出を発表しており、今後、インドにおける自動車産業地図が、大きく塗り替えられる恐れがある。
また、インドがグローバルなサプライチェーンに組み込まれてきていないという事情は、日本がこれまでベンガル湾を超えられなかったことに起因する。日本がベンガル湾を超えた地域秩序を再び構想できる可能性は限定的である。かつて著者はミャンマー南部を中核としたアジアのグローバル秩序の再編を構想し、奔走したが、残念ながらこうしたグレート・ゲーム、大戦略を仕掛けようという国家理性的な生理的衝動はこの国には、もはや無い。ビヨンドコロナ社会は完全に米国と中国の経済的な覇権争いを軸に展開されるだろう。GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)の世界戦略と、デジタル人民元など後発発展の利を享受するBATH(Baidu、Alibaba、Tencent、Huawei)など中国IT企業の台頭。これらに対抗して第三極を構築するには、日印の連携しかない。確かに足元では、インドはこのコロナ禍の大混乱でなかなか次の打ち手を見いだせずにいる。しかし、コロナ禍終息後の世界秩序では、日印の連携が基軸となり、特にデジタル分野での連携、インドのIT人財(ソフト)と、日本のものづくりの再編(ハード)によって新たなグローバル・ゲームを仕掛けることは可能ではなかろうか。
米国は、1980年代の日本に対する「経済敗戦」によって、1990年代にデジタル市場への展開が本格化していく。つまり米国では、日本のものづくりへの敗北がGAFAMの台頭を準備したとすれば、日本のものづくりは依然として、その技術やノウハウなどハードを活用できる余地がある。著者は、昨今の日本におけるスタートアップス信仰、シリコンバレー詣でや、「シリコンバレーでは」という説得方法で同意を調達する「でわのかみ話法」には懐疑的である。むしろ日本の進むべき道は、これまでの自動車産業を中心に、下請けとして「塩漬け」にされてきた中堅・中小企業の技術やノウハウを開放し、DX化とグリーン・リカバリ―の潮流を活用した新産業の創出に賭ける、「再創業」「事業再構築」、そして「リスタートアップス(Restart-ups)」を目指すべきであるという主張である。その際、インドのIT人財、就中(なかんずく)、人工知能(AI)やIoT(モノのインターネット)を中心としたデータサイエンスなどの人財は、日本のものづくりを高みに誘うことができるだろう。インドとの連携をこうした国家戦略的な視座で追求する必要がある。