インド理系トップスクールIIScのスタートアップ・インキュベーターについて
2024年12月2日 藤原 孝男(JSTアジア・太平洋総合研究センター 特任フェロー)
1. はじめに
2023年の主要国の経済成長率は、日本1.68%、アメリカ2.89%、中国5.25%、インド8.15%1であり、人口世界第1位のインドが2023年9月にはG20議長国となり、グローバルサウスの旗手として注目を集めている。インドは、1991年の外貨危機に伴う経済自由化や2000年代からの貿易増加を契機とするソフトウエアなどのサービス輸出超過にも関わらず貿易赤字のため、Make In Indiaを含め、特にディープテックスタートアップによる製造業の強化に力を注いでいる。ここではインド理系トップスクールであるIISc(Indian Institute of Science:インド理科大学)のスタートアップ・インキュベーターを対象に検討する。
2. IIScと経営研究科
IIScは設立が1909年と、1951年以降のインド工科大学(IIT)よりも早期で、首席科学顧問室の主席政策顧問が学内の科学技術庁政策研究センターを拠点にNDTSP(国家ディープテックスタートアップ政策)を立案しており、インキュベーションにおいても先導的役割が期待されている。
2024年3月の教員数は、研究科として機械科学132名、電気・電子科学81名、物理・数学80名、生物科学75名、化学46名などの他に、医学研究科開設に向けた教員も含めて計481名となる。また、2024年2月の学生数は博士課程が2,364名、修士課程2,010名、学部533名の降順であり、研究志向の大学と言える。2022年の学術誌論文2,546編、予稿集論文431編、図書収載論文78編であるが、研究成果の社会実装については、国内特許出願746件、海外特許出願315件、国際特許出願167件に加えて、創業支援において、全学的インキュベーター(STEM Cell)・各センターインキュベーター(2件)・研究室プロジェクトも含めるとTLO(技術移転機関)のFSID(科学革新開発財団)の支援対象企業は計56社になり、さらに卒業・自立した企業40社を加えると支援企業総数は計96社になる。
IISc内の経営研究科(Department of Management Studies: DoMS)では技術管理・金融工学などを中心に教員は8名であり、学生は博士課程30名、修士課程30人の計60名の大学院生のみが所属している。教員は学内インキュベーターの運営にも参加し、技術系起業家向けの経営に関する授業・セミナーを開催し、ベンガルールを始め国内外の起業経験者・VC・アクセラレーターなどの人脈紹介や政府委員会・産業界会合も含めて創業支援に積極的に協力している。
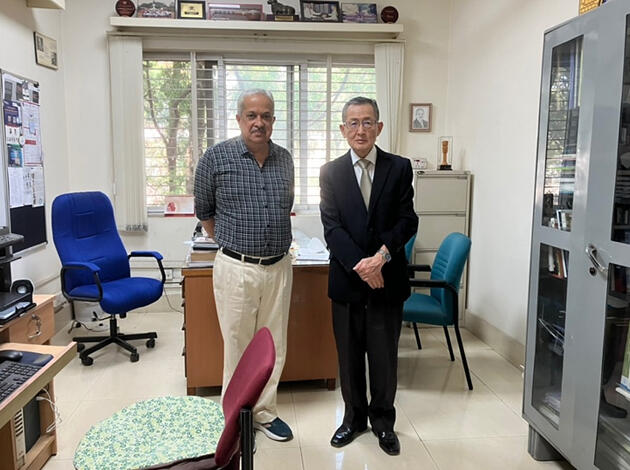
M.H.バラスブラマニア教授(左Prof. M.H. Bala Subrahmanya, Former Chairman)
2024年1月15日(月)IIScのDoMSにて
3. 産学連携組織のFSIDによる創業支援
IISc内での産学連携組織であるFSID(Foundation for Science Innovation Development: 科学革新開発財団)は、①全学対象のインキュベーターSTEM Cell、②CeNSE(Center for Nano Science and Engineering:ナノ科学工学センター)所属のナノ物質分野のインキュベーターInCeNSE(Technology Business Incubator at CeNSE)、③CPDM(Centre for Product Design and Manufacturing:製品設計製造センター)所属の2023年設立の医学技術・老齢医療分野のインキュベーターCPDMed TBI(MedTech & Geriatric Healthcare Technology Business Incubator at CPDM)の計3インキュベーターの支援を行い、他に大企業との共同研究、中小企業支援、農村支援の部局も有する。
(1)STEM Cell
STEM Cellは、中央政府のNITI Aayog(国立インド変革委員会)のAIMプログラム、MeitY(電子・情報技術省)のTIDE 2.0や、州政府のK-Techなどの各制度の支援を受けている。IISc内の全学科対象のSTEM Cellプログラムでは、学外者にも許可、教員向け、大学関係者向けの3プログラムがある。STEM Cellに入居企業21社(2013-2018年創業)の内の12社(57.1%)でIISc教員が、5社(23.8%)でIISc博士号取得者が、3社(14.2%)ではIISc修士号取得者が創業者である。業種としては、医療機器6社、バイオ4社、航空宇宙3社、AI 3社、環境技術3社、輸送1社、アグリテック1社の構成である。対象企業数の57%でIISc教員が創業者であり、IISc博士課程修了者も入れると80.9%になり、多業種にわたるが、大学の研究成果のスピンオフが順調であると言える。
スタートアップ例として、①Bellatrix Aerospaceは人工衛星用のプラズマスラスター(Plasma Thruster)開発に民間では世界初の成功を収め、②PolyMage Labs創業者はアメリカで博士号取得のIISc教授で、IBMやGoogleでの研究者の経験も有してコンパイラー・コードジェネレーターを開発し、③MiMYKは内視鏡訓練用AIシミュレーターと内視鏡を開発している(後述)。
(2)InCeNSE
CeNSE所属のインキュベーターInCeNSEは、カルナタカ州政府の資金援助を受け、ASML、AMD、Micron、サムスンなどと提携する同センターや、併設国立センターの特性解析施設、クリーンルーム、その他の専門的インフラの利用サービスを所属企業にも提供している。入居企業8社(2019-2022年創業)の内、IISc現役教授が創業者である企業は25.0%、IIScでの博士号取得者を入れると62.5%となる。業種としては、ナノ物質科学工学を基礎に、半導体デバイス3社、医療機器2社、品質管理などの半導体加工サービス1社、そしてクライオ(Cryogenic)電子顕微鏡を用いたバイオ創薬が1社である。
スタートアップ例として、①AGNITは創業者がIISc教授・CeNSEセンター長で、アメリカで博士号を取得し、有機金属化学蒸着法を次世代ワイヤレス機器向け窒化ガリウムパワー半導体用ウェハーに応用し、②TheranautilusはCEOがCeNSE教授で、ハーバード大学でポスドクを経験し、薬剤耐性細菌感染症・癌の治療向けのナノロボットを開発し、③ICeNDはクライオ電子顕微鏡を用いた量子ナノ物質・単一ナノ粒子流体工学の技術をバイオ創薬に応用する企業で、本社は、IIScで博士号を取得した創業者がThermo Fisher Scientific研究者を経験したオランダのアイントホーフェンにある。
(3)CPDMed TBI
CPDM所属のCPDMed TBIは老齢医療向けハードウエア開発のインキュベーターで、2023年にカルナタカ州イノベーション・技術部門の支援で設立されている。入居企業には、インキュベーター内のメディカルシミュレーション・電子工学、生物学等の各試験設備と、CPDMが所有する3Dプリンター、金属レーザールーター加工機、CNC工作機械、産業用ロボットなどの使用許可が与えられる。CPDMは、ハードウエア製品と製造システムの開発の研究教育を行なっている。CPDMの提携先としては、重工業庁の他、産業界ではToyota Kirloskar Motor、安川電機、海外の提携大学としてはハーバード大学、北陸先端科学技術大学院大学などが含まれる。

右上:B.グルムースィ教授(Dr. B. Gurumoothy, CEO FSID, Prof. of Mechanical Engineering & CPDM)
左上:C.S.ムラリ氏(Mr. C.S. Murali, Chairman of STEM Cell, FSID)
2024年2月5日(月)オンラインにて
4. STEM CellスタートアップのMIMYK
ミミック・メディカルシミュレーションズ社(MIMYK Medical Simulations Pvt. Ltd.)は、FSID・STEM Cell管轄のアントレプレナーシップセンター(Entrepreneurship Centre)内に入居し、VR・シミュレーション機能を有する医療機器としての内視鏡・同トレーニング機器を開発している。
企業の優位性として、①製品コンセプトから試作までの迅速開発、②高要求基準クリアの技術能力、③業界平均1/4の低コストなどを掲げ1個試作から前臨床試験での小ロット生産まで柔軟な生産形態を挙げている。専門的能力としては、①独自のイノベーション戦略立案、②人間工学、③機械工学、④電子工学、⑤イメージング・光学、⑥ピークパフォーマンス最適化のソフトウエア開発、システムアーキテクチュア、VR、⑦データコレクション、ビジョン・イメージ処理に対応可能な人工知能などに自信を有している。
共同創業者として、シャンタヌ・チャクラヴァルティ(Shanthanu Chakravarthy)CEOはIIScの機械工学で博士号、ニシン・シヴシャンカー(Nithin Shivshankar)CTOはIIScのコンピュータサイエンスで博士号、ラグ・メノン(Raghu Menon)COOはケンブリッジ大学で修士号を取得している。メンターとしてIISc元教授・Strand Genomics(現Strand Life Science)初代CEOでベンガルールのレジェンドでもあるDr. Vijay Chandru Reddyを含む多くの経験者が支援している。

前列左3人目:シャンタヌ・チャクラヴァルティ博士(Dr. Shanthanu Chakravarth, CEO)
前列左2人目:ラグ・メノン氏(Mr. Raghu Menon, COO)
1月16日(火)ミミック社(MiMYK: IISc, STEM Cell内スタートアップ企業)にて
(画像は全て筆者提供)
5. まとめ
DoMSのM.H.バラスブラマニア教授(Prof. M.H. Bala Subrahmanya)によれば、大学発スタートアップの事業領域として、ベンガルールは比較的全方位であり、凡そAI・IT系が70%、生命系が20%、残り10%がドローン・ロケット・人工衛星・環境・半導体の比率と推定している。生命系スタートアップへの外資系VC・PEによる投資は損益分岐点までの期間が長く、政治の安定性を注視するとのことであるが、モディ政権の継続で今後、アメリカの大規模ファンドによる中国からインドへの投資シフトが予測される。
FSIDのCEOグルムースィ教授(Prof.B.Gurumoothy)によれば、インキュベーター入居期間は平均4~6年で試作品等の概念証明によって卒業を決め、政府による健康履歴(Ayushman Bharat Digital Mission 下のhealth stack)の国民データが蓄積されるとAI学習用データとしてスタートアップ支援にも新しい機会が、学内に医学研究科ができると創業支援でも新しい展開がそれぞれ期待できるとしている。また、教員には週1日の自由な時間が与えられており、研究と事業化とは両立可能で、IP・インキュベーションへの学内の雰囲気はかなり肯定的で積極的な教員も多いとのことである。特に、IIScインキュベーションにおいて、全学的なSTEM Cellからナノ物質系のInCeNSE、さらに製造系のCPDMed TBIに至る各インキュベーターの設立推移は、首席科学顧問室のNDTSP下での製品コンセプトから試作化・生産技術への連結・強化を狙う社会実装戦略にも沿っているように思われる。
MIMYK創業者によると、外部の大学病院の教員と提携して医療データを収集し、診断・内視鏡手術に関するAI判断の精度を高めており、今後、国民の健康履歴データへのアクセスによる一層の精度向上が期待されるようである。現在、汎用内視鏡による手術のAIシミュレーション機の開発と、実用的な使い捨て内視鏡のThermo Fischer Scientificへの販売委託とを行っているが、将来的にはオリンパスとの棲み分けの可能性も検討したいとのことである。オランダのASMLからの転職研究者を含め、光学・機械工学・AIなど広い分野を比較的少人数でカバーし、若手で優秀な技術者集団が自由な雰囲気の中で開発している。
IIScのキャンパス内では教員・学生ともに自信に満ちた楽観的な表情であり、FSIDも日本の複数の大企業・大学とのMoUを協議中とのことである。特に、MIMYKを始め、人工衛星用のプラズマスラスター開発やクライオ電子顕微鏡を用いたバイオ創薬などの企業が際立っており、医学研究科の新設によってIIScインキュベーターには、今後、インドを牽引する一層の躍進が期待される。






