IITマドラス校における日印大学間交流
2025年3月31日

小林クリシュナピライ憲枝(こばやし・くりしゅなぴらい・のりえ):
長岡技術科学大学 IITM-NUTオフィス コーディネーター
<略歴>
明治大学文学部卒。日本では特許・法律事務所等に勤務した。英国に1年間留学、British Studiesと日本語教育を学ぶ。結婚を機にシンガポールを経てインドに在住。インドでは、チェンナイ補習授業校、人材コンサルティング会社、会計事務所に勤務後、現在は、長岡技術科学大学のインド連携コーディネーターを務めるとともに、インド工科大学マドラス校(以下IITマドラス校)の日本語教育に携わっている。IITマドラス校の職員住宅に居住している。
IITマドラス校では、現在、日本の大学、団体、企業からの訪問が急増している。その目的は、既存の学術交流の継続・強化にとどまらず、新たな学術協定の締結、年間またはセメスター留学、短期派遣、新規事業の案内、視察、調査など、多岐にわたる。
本年度の日本からの留学生については、インド政府奨学金を受けて修士課程に在籍する学生が1名、1セメスターから一年間の留学として、横浜国立大学、東京科学大学、九州大学から各1名が滞在、また、2週間から4か月の短期留学で、芝浦工業大学、東京大学、長岡技術科学大学からそれぞれ複数名が訪れた。
ここでは、今年度実施されたIITマドラス校と日本の大学との学生交流の事例を3つ紹介する。
芝浦工業大学とIITマドラス校の学術・文化交流
1) IITマドラス校での第7回アジア材料・加工シンポジウム2024(ASMP2024)での発表
(2024年12月5日~12月7日)
12月5日から7日にかけて、IITマドラス校で開催された一般社団法人日本機械学会のASMP2024において、芝浦工業大学の修士課程2年生が研究発表を行った。
そして、この機会に、その後日本留学をする学生達との交流もできた。

(写真はプログラム参加学生の提供)
2) IITマドラス校における芝浦工業大学の語学研修プログラム
(2025年2月24日~3月7日)
このプログラムは今年で10回目を迎えた。オープニングには、駐日インド大使のシビ・ジョージ大使からのビデオメッセージが披露され、長年にわたる両校のコラボレーションの成功例を示した。
学生達は、12日間にわたって、特別に設けられた技術英語クラスを受講。そして、大学のヘリテージセンター、リサーチパーク、センター・フォー・イノベーションといった主要施設を見学し、最先端の研究環境を体験した。文化体験としては、マリーナビーチ、サントメ大聖堂、世界遺産のマハーバリプラムなど、チェンナイの象徴的なランドマークを巡り、インドの豊かな歴史と文化に触れた。さらに、学内では、ヨガセッションやクリケット体験などを通じて、IITマドラス校の学生達とスポーツを楽しみながら異文化交流を深めた。

(写真はIITMマドラス校の提供)
東京大学におけるさくらサイエンスプログラムと、IITマドラス校におけるインド体験活動
1) 東京大学におけるさくらサイエンスプログラム
(2024年12月12日~12月16日)
東京大学は、IITマドラス校とIITハイデラバード校からそれぞれ3名を「さくらサイエンスプログラム」に招待した。IITマドラス校からは、日本語授業を履修した学生の中で、成績優秀者3名が選ばれた。
プログラムでは、大学紹介、キャンパスツアー、ラボ見学、講義の聴講、日本語授業への参加、茶道体験などを実施。その後、石巻南浜津波復興祈念公園を訪れ、東日本大震災の被害と復興の歩みについて学んだ。また、池袋防災館での防災体験から、日本の防災への取り組みも学んだ。さらに、日本科学未来館では、日本の最新の科学技術に触れた。プログラムの締めくくりとして、参加者全員がこのプログラムから学び得た経験を発表した。短期間ながら、学びの多い充実した日々を過ごした。

(写真はプログラム参加学生の提供)
2) IITマドラス校におけるインド体験活動
(2025年2月17日~2月23日)
IITマドラス校は、東京大学からのインド体験希望者8名を受け入れ、交流を深めた。
東京大学の学生達は、日本語授業に参加し、大学紹介と日本の食文化について発表。授業のサポートも行い、現地の学生との交流を図った。また、夕刻には、学内の希望者に向けて、折り紙、書道、浴衣の着付け、盆踊りなどの日本文化を披露した。この行事には200名ほどの参加者があり、大盛況であった。さらに、学内の複数の学科や、リサーチパークも訪れた。
市内観光やマハーバリプラム訪問などを通じ、インドの文化や歴史にも触れた。IITマドラス校での滞在を終えた後は、デリー観光に向かった。
両校の学生達は、双方向の交流を通じて、互いに有益な学びの機会を得ることができた。

(写真はIITマドラス校の提供)
長岡技術科学大学とIITマドラス校の学術交流
1) IITマドラス校での第7回アジア材料・加工シンポジウム2024(ASMP2024)での発表
(2024年12月5日~12月7日)
12月5日から7日にかけて、IITマドラス校で開催された一般社団法人日本機械学会のASMP2024において、長岡技術科学大学の博士課程の学生がポスター発表を行い、修士課程1年生が研究発表を実施した。
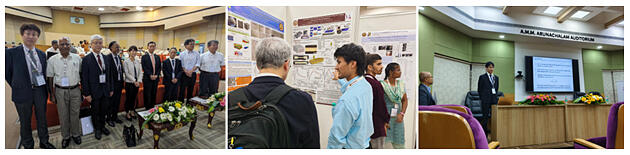
(写真は筆者撮影)
2) 長岡技術科学大学でのDX Manufacturing Workshops 2024で両大学の共修
(2024年12月18日)
長岡技術科学大学とIITマドラス校では、世界展開力強化事業の一環として、両校の学生が主体となって企画した「DX manufacturing Workshops 2024」を、12月18日に開催した。本ワークショップは、対面とオンラインのハイブリッド形式で実施され、計42名(対面24名+オンライン18名)が参加した。ワークショップでは、生体材料、トライボロジー、トポロジー最適化、メタマテリアルといった多岐にわたるテーマが取り入れられ、領域横断型のパネルディスカッションを実施。参加者同士が活発に意見を交わし、今後のAM (アディティブ・マニュファクチャリング) 技術のあり方について議論を深めた。
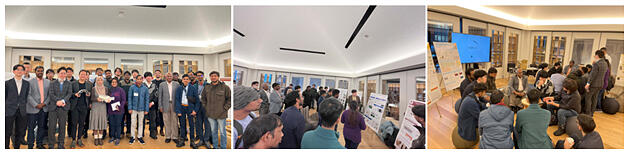
(写真は長岡技術科学大学の提供)
また、同大学と、溶射技術のプラズマ技研工業(株)の産学連携では、IITマドラス校の学生を研究インターンシップで毎年受け入れている。
さらに、さくらサイエンスプログラムでも、IITマドラス校の学生の受け入れを行った。
3) IITマドラス校での実務訓練と研究インターンシップ
(各自個別のプログラム・期間で、2024年10月~2025年2月の間)
長岡技術科学大学は、10年以上にわたり、学部4年生の実務訓練生をIITマドラス校に派遣してきた。今年度は、生物系の学生1名がバイオテクノロジー学科で4か月間の実務訓練を経験した。
また、同大の大学院生6名が、各自の専門に応じた学科の研究室で研究インターンシップを実施。そのうち、産学連携で、大学の研究室とリサーチパークのスタートアップ企業SatoriXRの2か所で研究をしたケースがある。また、研究インターンシップ中に執筆した論文が受理され、その後ニューデリーで開催された国際会議(GRIDCON2025) で発表を行ったケースもあった。

(写真はプログラム参加学生の提供と筆者撮影)
交流を通じた相互の学びと刺激
以上の交流を通じて、インドの学生からは、日本の戦後復興や経済成長の歴史、日本の学生の、誠実で礼儀正しく、また研究熱心な姿勢に対する敬意の声が複数聞かれた。
一方で、日本の学生は、インドの学生の高い英語力、自主性、熱意に感心し、大いに刺激を受ける場面が多く、インド社会への関心が深まるきっかけとなったケースも多く見られた。
これらの貴重な経験を糧に、彼らが未来の社会を正しく導く存在へと成長していくことを期待している。





