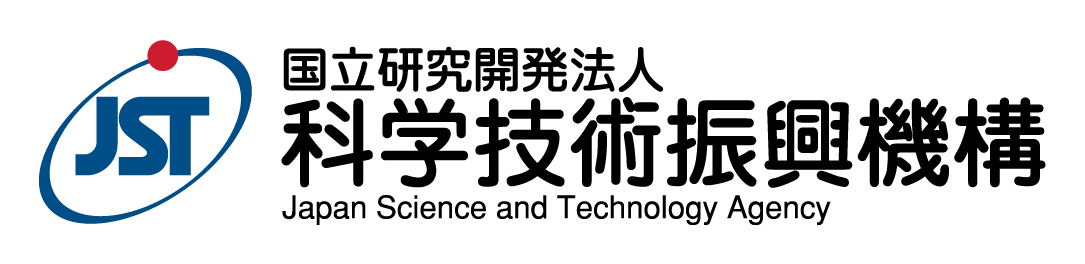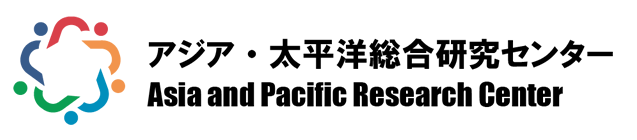最先端のイメージング技術でDNA鎖の積み重なり方を解明 インド
インド理科大学院(IISc)の生化学部の研究者らが、新しいイメージング技術を用いて、DNAの構成要素である塩基が、隣接する塩基とどのように結合しているかを突き止めた。8月18日付け発表。研究成果は学術誌Nature Nanotechnologyに掲載された。
生物の遺伝子情報を担うDNAは、アデニン(A)、グアニン(G)、チミン(T)、シトシン(C)の4つの塩基が連なって構成されたDNA鎖2本が対をなした2重らせん構造をとっている。このような構造は2種類の相互作用によって安定している。2本鎖の塩基間の相互作用はよく知られているが、塩基のスタッキング相互作用と呼ばれる1本のDNA鎖において隣接している塩基間の相互作用についてはあまり研究されていなかった。
IISC生化学部のマヒバル・ガンジ(Mahipal Ganji)准教授らはA、T、G、Cの4塩基による16通りの塩基スタッキングの組み合わせを調べるために、DNA-PAINT(Point Accumulation in Nanoscale Topography)を使用した。DNA-PAINTは、2本の人工的に設計されたDNA鎖を室温の緩衝液に入れると、ごく短時間の間にランダムに結合や分離を繰り返す原理を利用したイメージング技術で、研究チームは鎖同士が結合したときに発光するように蛍光色素を用いて実験を行った。
実験の結果から、隣接した塩基間の相互作用が強いときに、鎖の結合と結合解除にかかる時間が長くなることが分かった。さらに、DNA−PAINTで得られたデータを用いて、結合と結合解除のタイミングを、隣接した塩基間の相互作用の強さを関連付けるモデルを構築した。これにより、DNA鎖に塩基のスタッキング相互作用を1つ加えるだけで安定性が最大250倍になることが分かった。またヌクレオチド対はそれぞれ独自のスタッキング強度を持つことも分かった。
これらの成果により、高効率の3本アームDNAナノ構造を設計し、多面体形状のビークルに組み込むことで特定の疾患マーカーを標的にしたりするような生物医学的応用ができる可能性があると研究者らは語る。ガンジ准教授は「この研究成果が、1本鎖および2本鎖DNAの基本的な性質の研究に利用され、ひいてはがんを含む多くの病気の原因となるDNAの修復機構の解明につながることを期待している」と話した。
サイエンスポータルアジアパシフィック編集部