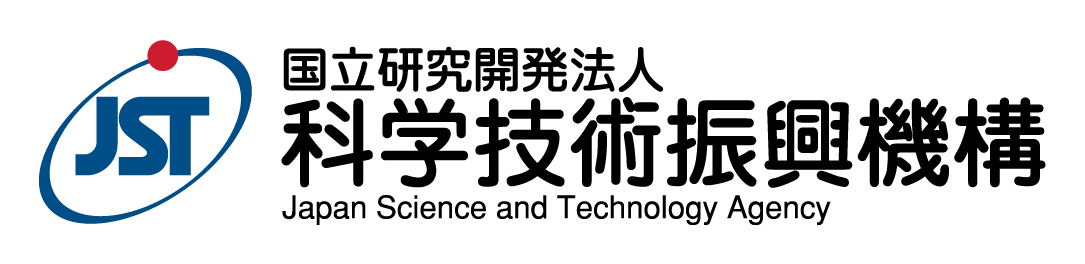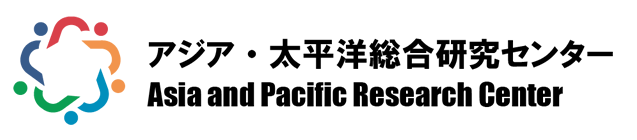パーキンソン病治療法の最適化に向けたシミュレーション技術を開発 インド
インド工科大学マドラス校(IIT-M)は10月1日、同大学研究者による、シミュレーション技術を用いたパーキンソン病の治療法について発表した。この研究成果は、学術誌Brain Sciencesに掲載された。
パーキンソン病は、アルツハイマー病に次いで高齢者に多い神経変性疾患である。主な原因はドーパミンの欠乏だと考えられており、震え、動作緩慢、筋肉の硬直、バランス能力の低下などの症状を引き起こす。高齢化が加速する今、パーキンソン病の治療法の発見や管理方法の確立は急務である。
注目されている治療法の一つに脳深部刺激療法(DBS)という、外部から電流を用いて特定の脳領域を刺激する技術がある。DBSは、薬物治療で十分な効果が得られない場合や副作用が深刻な場合に有効で、薬でドーパミンを補充するL-DOPAと組み合わせることで治療効果が高まることが知られている。
IIT-M物理学部のサンディープ・サティアナンダン・ナイール(Sandeep Sathyanandan Nair)氏とスリニヴァーサ・チャクラヴァルティ(Srinivasa Chakravarthy)教授は、パーキンソン病の運動症状に対するDBS刺激の計算モデルを開発した。日常生活に欠かせない腕の到達動作を対象とし、その運動症状を再現するためのシミュレーションモデルを開発した。
この研究モデルで再現された到達動作中の運動パフォーマンスは、実験データと一致する結果を示したことから、このモデルを用いることで、パーキンソン病患者が経験する具体的な運動障害の理解を深め、DBSによる運動機能の回復効果を評価できるようになると期待される。
インド工科大学ボンベイ校(IIT-B)のロヒト・マンチャンダ(Rohit Manchanda)博士は、「一般的に、DBSはバランス能力低下を悪化させるため、バランス能力に問題のある患者への適用は推奨されません。しかし、今回開発した手法では、弱い電流でのDBSでも効果が得られる条件についても検証しています。そのため、この手法が実現すれば臨床的に大きなインパクトが期待され、神経科学と臨床介入の両分野にとって重要な貢献となるでしょう」と述べた。
サイエンスポータルアジアパシフィック編集部