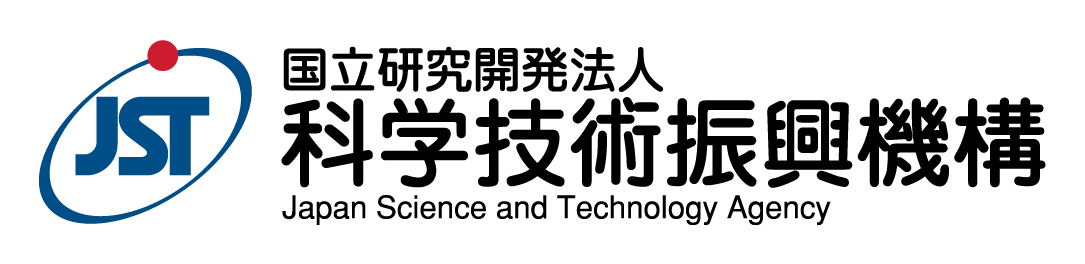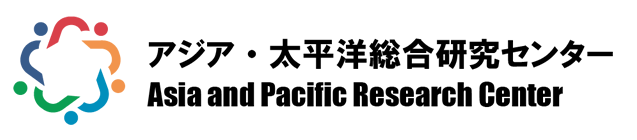【The Conversation】 量子もつれに新たな進展、原子核をつなげ量子コンピューターを身近なものに
かつて、アルバート・アインシュタインは量子もつれに納得せず、「不気味な遠隔作用」と呼んだ。それにもかかわらず、量子もつれは長きにわたり人々の想像力を掻き立ててきた。また、経験豊富な科学者さえも困惑させてきた。
しかし、今日の量子の研究者にとって、量子はもっと日常的なものとなっているのが現実である。量子もつれとは、粒子間のつながりの一つの形であり、量子コンピューターの本質的な特徴である。
量子コンピューターはまだ初期段階であるが、量子もつれを利用すれば、例えば分子、医薬品、触媒について、自然界の量子システムのシミュレーションを高い精度で実施することができる。これは従来のコンピューターでは不可能であった。
筆者を含むチームは新たな研究を行い、約20ナノメートル離れた2つの原子核間の量子もつれを実証し、本日、Science誌に公開した。
これは大きなニュースとは思えないかもしれない。しかし、チームが用いた方法は、実用的かつ概念的な進展となり、量子情報を保存するにあたり最も正確かつ信頼性の高いシステムの一つを利用する量子コンピューターの構築に役立つと考えられる。
制御とノイズのバランス
量子コンピューターエンジニアが直面する課題は、相反する二つのニーズのバランスを取ることである。
脆弱な演算部分については、外部からの干渉やノイズから保護されなければならない。しかし同時に、有意義な計算を実行するためには、それらと相互作用することも必要である。
そのため、世界で初めて作動する量子コンピューターを目指して、今もなお様々な種類の機器が競争を繰り広げている。
高速演算に非常に優れてはいるが、ノイズの問題を抱える機器もある。だがノイズから十分に保護されてはいるが、作動やスケールアップが難しい機器もある。
原子核同士に通信させる
筆者のチームは、今日まで後者に属するプラットフォームの開発に取り組んできた。シリコンチップにリン原子を埋め込み、原子核のスピンを利用して量子情報の符号化を行ったのである。
実用的な量子コンピューターを構築するには、多数の原子核を同時に扱う必要がある。しかしこれまで、複数の原子核を扱う唯一の方法は、固体内に原子核を密集させ、1個の電子で囲むことであった。
一般的に、電子は原子核よりもはるかに小さいと考えられている。しかし、量子物理学の考えでは、電子は空間的に「広がる」ことができるため、複数の原子核と同時に相互作用することができる。
とはいえ、1個の電子が広がる範囲は非常に限られている。さらに、1個の電子に対し原子核を追加すると、それぞれの原子核を個別に制御することが非常に困難になる
遠く離れた原子核を絡ませる電子「電話」
今までの原子核は、防音室の中にいる人々のようなものだと考えればよい。同じ部屋にいる限り、互いに非常に明瞭な会話をすることができる。
しかし、外部の音は聞こえず、部屋に入れる人数にも限りがある。そのため、この会話方式をスケールアップすることはできない。
チームの新しい研究は、人々に電話を与えて他の部屋とコミュニケーションを取ろうとするようなものである。それぞれの部屋は快適であり、静かなままであるが、遠く離れた多くの人々と会話できるようになる。

「幾何学的ゲート」を介して電子と絡み合った二つの原子核の概念図
(Tony Melov / ニューサウスウェールズ大学シドニー校)
この「電話」とは電子のことである。電子は空間に広がる性質を持っているため、2つの電子はかなりの距離からでも「接触する」ことができる。
そして、それぞれの電子が原子核に直接結合していれば、原子核は電子間の相互作用を介して通信することができる。
チームは電子チャネルを用いて「幾何学ゲート」と呼ばれる手法で原子核間の量子もつれを作り出し、数年前にシリコン中の原子を用いた高精度の量子演算に用いた。
今回は、シリコンの中で初めて、この手法は1個の電子に結合した原子核のペアにとどまらず、スケールアップできることを実践した。
集積回路への組み込み
チームはリンの原子核を20ナノメートル離して実験を行った。これはわずかな距離に思えるかもしれない。その通りである。二つのリン原子の間には40個に満たないケイ素原子が存在するだけである。
しかし、これは日常的に使用されるシリコントランジスタが製造される規模でもある。20ナノメートルという大きさの量子もつれ状態を作り出すことで、長寿命で優れた遮蔽性を備えた核スピン量子ビットを、スマートフォンやコンピューターに搭載されている標準的なシリコンチップの既存アーキテクチャに統合できる。
電子は物理的に移動させたり、細長い形状に押しつぶしたりできるため、将来的には、量子もつれの距離をさらに長くすることができると考えている。
今回の画期的な大発見は、電子を利用する量子機器の進歩は、長寿命の核スピンを用いて信頼性の高い計算を実行する量子コンピューターの構築に応用できることを示している。
(2025年10月9日公開)