【AsianScientist】 環境保全戦略策定に先住民の伝統的な知識体系を活用
アジアの環境研究者や政策立案者は、先住民コミュニティと協力して伝統的な知識体系を活用し、環境保全について優れた戦略を策定する。(2025年7月24日公開)
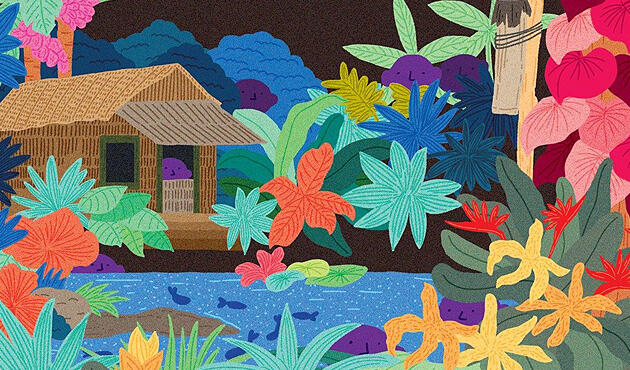
タイの少数民族の中でも最大である山岳民族のカレン族では、赤ちゃんが生まれると、コミュニティの長老たちが赤ちゃんのへその緒を切り、竹の器に入れて、健康な果樹に吊るす。
アジア先住民族協定 (AIPP) のカレン族環境プログラム担当官であるピラワン・ウォンニティサタポン (Pirawan Wongnithisathaporn )氏は「こうすることで、赤ちゃんの魂と木の魂は生涯にわたって繋がれ、誰もその木を切ることは許されません」と語る。AIPPはタイのチェンマイに拠点を置く非営利団体であり、この地域の先住民族の権利を主張し、擁護している。「私たちは自然の摂理に反して生きることはできません。だからこそ、私たちの生活は持続可能なのです」
世界には、昔から生存の糧となる自然生態系を育み、それに依存してきた多くの先住民コミュニティがあるが、カレン族はそれらの一つに過ぎない。しかし、生物多様性と生態系保全に関する政府間科学政策プラットフォーム (IPBES) の2019年報告書によると、カレン族の意見や権利は、地域・地球規模の環境・気候計画において、ないがしろにされることが多かった。IPBESは94か国の政府からなる独立した連合体であり、生物多様性と生態系保全に関する科学と政策の連携の強化を目的としている。
しかし、IPBES報告書の中で述べられているように、先住民の知識は、コミュニティの生活の質だけでなく、広範な保全活動や環境カバナンスを作り出す上で非常に貴重なものとなる。この点は、2022年にBiological Conservation誌に発表された報告でも重視されていた。報告は、先住民コミュニティは地域の生態系に直接依存し、その変化を観察し、解釈し、世代を超えて伝えることで、生態学的特徴に関する詳細な知識を得ていると指摘している。報告書には「先住民は科学者よりも地域の生物多様性と環境変化に関する情報を詳しく知り得る立場にいる」というIPBSの論文が引用されている。
国際労働機関 (ILO) によると、世界の先住民の約3分の2がアジアに居住している。このことから、アジアの政策立案者や環境研究者は、先住民が環境保護において果たす重要な役割を認識し、持続可能な保全策や包摂的な気候変動政策の開発に先住民を関与させ始めている。
ウォンニティサタポン氏は、こうした協力はすでに地域社会や生態系に良い結果をもたらしているものの、その多くは依然として小規模で局所的なものだと述べている。「私たちは、こうした取り組みを大規模に拡大し、法的支援を得たいと考えています」Asian Scientist Magazine誌では、アジアの事例をいくつか紹介する。
水の恵みを取り戻す
1980年代後半から1990年代初頭にかけて、マレーシアのサバ州のいくつかの村で爆破漁法という破壊的な漁法が行われ、魚の個体数が急激に減少した。爆破漁法では、灯油と肥料の入った瓶で作られた安価な自家製爆弾を使用して、大量の魚を無差別に殺した。
サバ州最大の先住民集団であり、稲作農業を営むカダザンドゥスン族は、この危機に対し、タガルを復活させることで対応した。タガルとは河川で持続可能な漁業を行うために伝統的に用いられてきた先住民の知恵である。保護が必要な河川はタガルに基づき、赤、緑、黄色の3つのゾーンに分けられる。赤のゾーンでは漁業が禁止され、黄のゾーンでは特定の時間帯のみ許可され、緑のゾーンではいつでも漁業が可能である。黄のゾーンでは、毎年又は半年に一度、関係する委員会が決定した日程に合わせて漁業が行われる。この先住民コミュニティは灰色の川原粘土を使った陶器作りの技術で知られている。タガルの実施は地元の村議会と協力し、河川の管理と監視は各保護河川区域の住民委員会が担当した。
その後、川の魚の個体数が回復したことを受け、サバ州水産局は2003年にタガル制度を保全戦略として採用した。現在、タガル制度はサバ州の内水面漁業管理制度の一部として扱われ、227の川の628のゾーンが水産局によって正式なタガルとして登録されている。
タガル制度を導入したところ、2024年には黄のゾーンで600キログラムの漁獲量があり、スンガイ・ピサパカン・ドゥンピリン・タガル委員会の委員長であるエジロン・トンギアック (Edjilon Tongiak) 氏にとって明らかな結果が出た。同氏は2024年の報告書で「委員会メンバー全員と村民の協力なしには、この豊漁はあり得なかった」と語っている。
温暖化する山々を駆け巡る
2018年、ブータン農林省の研究員であるケサン・ワンチュク (Kesang Wangchuk) 氏は、温暖化が高山の牧草地とヤクに与える影響について精査するために、研究チームを率いてヒマラヤでヤクを遊牧する先住民のうち100名の高齢者たちと接触した。研究者たちは、遊牧民との話し合いを通して、遊牧民その他の地元の人々の生活に対する気候変動の影響を軽減する戦略を策定しようとした。
ブータンでヤクを放牧しているビョブ族やブロクパ族は、ブータンの人口の5%未満を占めている。標高3000フィート(約900メートル)では、昔から、ヤクやヒツジがここのコミュニティの生活に不可欠な肉、乳製品、肥料、毛を提供してきた。
高齢の遊牧民たちは、数十年にわたる直接の観察から、気温上昇によって高山の雪線と植生はさらに高度に移動し、それに伴い、家畜の放牧のために従来よりも遠方まで移動せざるを得なくなったと語った。また、降雨量の増加による鉄砲水や土砂崩れの増加、ヤク乳の生産量の減少、そしてトラやユキヒョウといった家畜捕食動物がコミュニティ周辺で増加したことも話してくれた。
この研究は、「遊牧民たちが持つ幅広い認知と認識は、様々な指標を通して気候変動を包括的に捉える能力を示しているだけでなく、彼らの恐怖と懸念を反映している」と報告している。
近年、ブータン政府は、遊牧民コミュニティの知識と経験を活用して、気候変動に対する高山コミュニティと放牧地の回復力を高めようとしている。2019年、政府はブータン高原に広がる多数の遊牧民コミュニティと協同組合を連携させようと、ブータンヤク連盟 (BYF) を設立した。BYFは開発機関と協力し、ヤクの飼育と牧草地管理に関する伝統的手法と現代的手法の組み合わせを支援している。これには管理野焼き、放牧地共同管理、技能訓練、多様な畜産物などが含まれる。
2024年、ブータン研究センターの研究員であるチミ・ワンモ (Chimi Wangmo) 氏は、ブータンのヤク遊牧民が直面する課題に関するレビュー論文を発表した。その論文の中で、BYFは全国の1067世帯のヤク遊牧民世帯から構成されていると書かれている。 研究者たちは「全国の遊牧民が社会経済的要因や気候変動の影響など、同じような変化の要因に直面していることを認識し、BYFはヤク遊牧民と高地の研究開発に関わる様々な利害関係者による集団的かつ団結した行動の必要性を強調している」と語る。
3Dマッピングによる森林保護
カンボジア東部に位置するケオ・セイマ野生生物保護区 (KSWS) は、約3000平方キロメートルの熱帯混合林を囲む地域であり、959種の植物、菌類、動物が記録されている。そこでは、ブノン族をはじめとする先住民族が、長年にわたり森林と共存し、互いに支えあいながら暮らしてきた。気候変動と森林破壊に直面する中、ブノン族は現在、地元機関や国際機関と協力し、森林パトロールから炭素金融の推進まで、幅広い保全活動を行っている。
2024年8月、ブノン族のプトロム村の住民と指導者30名以上が、KSWSの持続可能な景観と森林管理を目的とするパイロット3Dマッピング研修に参加した。この研修は、米国国際開発庁、米国航空宇宙局、アジア防災センターの共同パートナーシップであるSERVIR SEAによって主催された。SERVIR SEAは、公開されている衛星画像と地理空間技術を活用し、この地域の気候変動問題に取り組んでいる。
ワークショップでは、参加者は技術専門家と一緒になって、プトロム村の多色3Dモデルを作成した。このモデルは高低差を示し、土地利用型がはっきりと分かる。研修の後には、土地利用計画に関するグループディスカッションが行われ、参加者は農業又は保全に適している土地について理解することができた。
ワークショップ参加者のヨウン・サスヴィス (Yoeun Sasvith) 氏はSERVIR SEAのイベント後、報告書で、「この研修は、景観に対する私の理解を大きく変えました。地域をより詳細に把握することができましたし、これは保全活動の計画に不可欠です。この新たな知識を得たことで、意思決定を行い、地域社会のニーズを訴える力がより強くなったと感じています」と述べている。SERVIR SEAのジェンダー平等と社会的包摂担当リーダーであるチャイナポン・ミーチャイヤ(Chinaporn Meechaiya) 氏は、同じ報告書の中で、先住民コミュニティと3Dマッピング研修を実施することで、地域の景観への理解が深まり、疎外された人々の声を大きく伝えることができると付け加えている。他の地域団体も、SERVIR SEAと協力し、同様の研修に参加するようになってきている。
認識の変化
南アジアと東南アジア10か国の国家気候変動政策を検証した2024年のAIPP報告書は、政策に先住民の権利、役割、知識を組み入れると、先住民族が政策立案に参加しやすくなると指摘している。
このような見識に基づき、報告書は今後2年間、各国は地方政府および関係者の実行力を高め、先住民コミュニティの権利が尊重されるようにすることを推奨している。また、先住民の男性、女性、若者、障害者が積極的に環境と気候の政策策定プロセスに参加でき、そのために必要な情報と資源が利用できる仕組みを確立するよう求めている。
最近、アゼルバイジャンのバクーで国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) 第29回締約国会議が開催されたが、その閉会式でも同様のことが改めて強調された。この会議で採択されたバクー作業計画は、気候危機への取り組みの中での先住民族と地域社会のリーダーシップを重要視している。
最近では、タイのクンチェー国立公園内のカレン族コミュニティであるヒンラートナイ村の保全活動が国際的に知られてきている。1980年代の大規模な森林伐採の後、ヒンラートナイ村では伝統的に行われてきた輪作農法が復活した。現在、この農法は土壌の健全性維持と炭素の隔離に役立っていることが知られており、クンチェー国立公園では、以前伐採された森林の約80%が過去30年間で回復したと推定されている。
国際非営利団体であるフードタンクが2023年に発表した報告書は、コミュニティのカーボン・フットプリントに関する調査を特に取り上げた。この調査はヒンラートナイ村、タイの研究者であるプラヨン・ドクラミャイ(Prayong Doklamyai) 氏、そしてオックスファム・インターナショナルと共同で実施したものである。調査によると、輪作農法は、その一部である管理野焼きが年間約480トンの二酸化炭素を排出する一方で、ヒンラートナイ村の再生型休耕方式では、年間1万7000トンの二酸化炭素を貯留していることが示された。
カレン族の研究者であるプラサート・トラカンスパコン (Prasert Trakansuphakon) 氏はフードタンクの報告書の中で「西洋諸国では、輪作農法は森林破壊の原因であるという議論がされています。しかし、ヒンラートナイ村は科学的研究を通じて、輪作農法が気候変動を引き起こしているのではなく、むしろその逆であることを証明しました」と語る。





