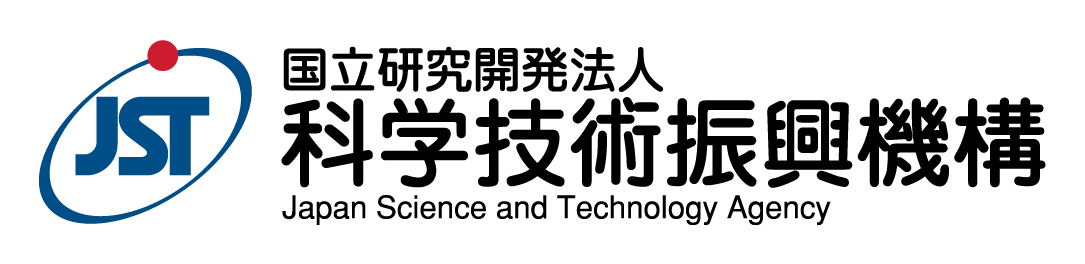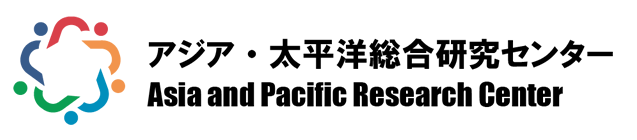アジアのチェンジメーカー:ウン教授、終わることの無いパンデミックとの戦い
2021年5月27日 AsianScientist
ウイルス免疫学の第一人者であるリサ・ウン(Lisa Ng)教授が、疾患を引き起こす病原体との闘いに、最新ツールを導入する。

AsianScientist - コロナウィルスによるパンデミックに、現在、世界中が驚かされているが、このようなアウトブレイクは今に始まったことではない。聖書にある疫病から中世の天然痘まで、感染症は太古から人間社会を攻撃してきた。14世紀の黒死病を例に挙げると、細菌のペスト菌が原因である腺ペストにより、当時の欧州の人口の約半数に当たる命が奪われ、2億人に達する死者数を記録している。
痘瘡ウイルスに起因する天然痘は、1980年に正式に根絶が宣言されるまで20世紀だけでも約3億人の人々を死に追いやった。一方、長期にわたるヒト免疫不全ウイルス(HIV)の流行は、1981年に初めての症例が報告されて以来、約7600万人の人々を感染させてきた。これらの数字を考慮に入れると現在のアウトブレイクは比べ物にならない。100万人もの死者を出し、その数は今も増え続けていることを踏まえると、新型コロナウィルスはおそらく現代で最も重大なパンデミックであり、しかもこれが最後となる可能性は低いかも知れない。
疾患を引き起こす病原体との長年の闘いの最前線に、リサ・ウン(Lisa Ng)教授は立っている。ウン教授はシンガポール科学技術研究庁(Agency for Science, Technology and Research's:A*STAR)のシンガポール免疫ネットワーク(Singapore Immunology Network:SIgN)で上級主任研究員を務めている。マンチェスター工科大学で生化学の学部生であった若い時期から、ウン教授はすでに感染症に強い関心を抱いていた。その思いがシンガポール国立大学での分子ウイルス学の博士号の取得につながり、さらにシンガポールのA*STARのゲノム研究所で博士課程を修了した後も研究を進めてきた。
その後20年間にわたり、ウン教授は、シンガポールにおける感染症に対して、科学的な対策を講じる際の重要な役割を担うようになった。博士論文ではコロナウィルスを研究し、博士号取得後はすぐにA*STARの診断研究チームの一員として採用され、2003年のSARSの流行時も含め、数年間勤務を続けた。ウン教授は同僚とともに、患者の血液サンプル中のSARS-CoVの検出を可能にする検査法を開発した。その後、チクングンヤ熱のバイオマーカーの確立に加え、鳥インフルエンザやジカの診断検査法の考案にも貢献した。
ウン教授の豊富な経験が計り知れないほど貴重であることが、最新のコロナウィルスとの闘いにも生かされた。昨年7月には、ウン教授は共同研究者とともに、比較的軽度の新型コロナウィルス感染症に関連のあるSARS-CoV-2変異体の発見についての論文を学術誌Lancetにて発表した。この変異体は感染した患者で免疫応答を誘発するが、過剰な炎症に至ることはないため、潜在的な生ワクチンとして期待が示唆されている。
ウン教授は、「我々の研究によってシンガポールは有名になったことと思います。我々は、保健省やデューク-シンガポール国立大学医学校、国立感染症センター(NCID)から集まった研究者たちによる共同研究を行いましたが、これは実に有意義な取り組みでした」と語る。
学術誌Nature Communicationsで発表した別の研究では、ウン教授の研究チームは、新型コロナウィルスの患者から得た抗体によって認識されたSARS-CoV-2の表面上の2つのタンパク質の特定にも成功した。教授によると、これらのタンパク質は、集団におけるコロナウィルス感染の真の範囲を判定するアッセイに活用できるとのこと。これらは、さまざまなワクチン候補によって発生した免疫応答を臨床試験で評価する際に役立つ。驚くべきことに、この研究の大部分は、シンガポールにおける「サーキット・ブレーカー」と呼ばれる感染封じ込め策の期間中に行われた。
「たった1件の実験をするために、数々のハードルを越えなければなりませんでした。SARS-CoV-2で研究することは非常に危険であったため、研究すること自体が挑戦でした。研究を始める際、生物学的な封鎖のトレーニングや多数の規制要件を満たさなければなりませんでした。安全なディスタンスをとるため、作業者を分ける必要にも迫られました」とウン教授は振り返る。
「終わることのない難題」にもかかわらず、ウン教授は、新型コロナウィルスのパンデミックから多くの教訓が得られ、それらは今後実験室の壁を超えて確実に役立つとともに、将来のアウトブレイクでも有益となると考えている。
「人間は、本質的に打たれ強いことがお分かりいただけると思います。私も研究チームも、決して諦めませんでした。心地よい領域からも抜け出し、成長のための重要な一歩を踏み出すことを恐れてはいけないのです。」