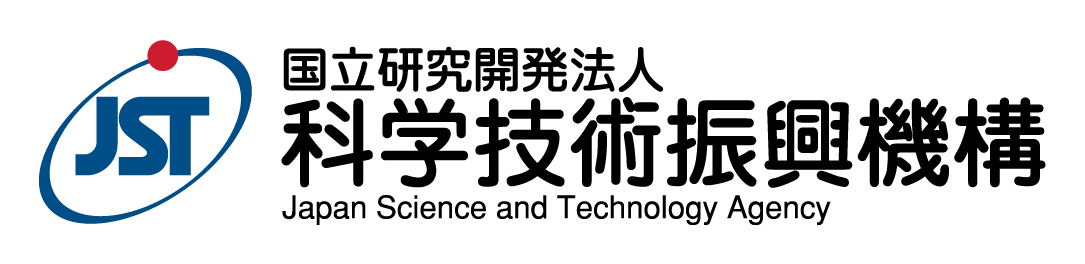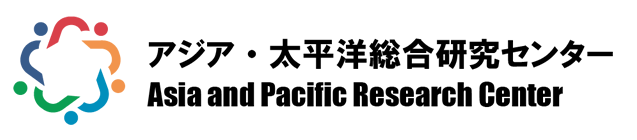メタン酸化細菌の培養に成功、気候変動課題に対応 インド
インド科学技術省(MoST)は8月5日、アガカール研究所の研究チームが、西インドの水田や湿地から国内初のメタン酸化細菌(メタノトロフ)を培養し、今後の気候問題への対応に役立つ可能性があると発表した。研究成果は学術誌Indian Journal of Microbiologyに掲載された。

(出典:PIB)
メタンは、二酸化炭素(CO2)の26倍の温室効果を持つ、地球温暖化にとって2番目に重大な温室効果ガスで、メタン生成菌の作用により生成される。一方、メタノトロフは、酸素を呼吸しながらメタンを酸化し、CO2と水を生成してバイオマスを形成する細菌で、湿地や水田、池などの水域で豊富に生息する、いわば天然のメタン緩和剤だ。
アガカール研究所のモナリ・ラハルカール(Monali Rahalkar)博士が率いる研究チームは、西インドを中心とした水田や湿地からインド初となるメタノトロフを分離し、新属新種であるMethylocucumis oryzaeを発表した。このメタノトロフは、キュウリのような特徴的な楕円形で細長い形状をしているため、「メタンを食べるキュウリ」という名前が付けられた。研究チームは、このメタノトロフを分離した後、数年後には水田から類似の微生物を培養することにも成功した。また、このメタノトロフが、インド・プネーにある石切り場に豊富に存在していることも発見し、この場所で活発なメタン循環が行われている可能性があることが示唆された。
Methylocucumis oryzaeは、他の国や地域からは報告されておらず、約10年前に初めて分離され、約6年前に論文で発表されたが、これまで、系統学的に独特な存在であり続けている。このメタノトロフは、3~6µmと他の細菌と比べて非常に大きく、厳密な中温菌で37℃を超えると増殖できない。また、淡いピンク色のコロニーを形成し、そのゲノムにはカロテノイド経路が示唆されている。
このメタノトロフは、稲の早期開花と穀物収量の増加を促進することが確認されており、地元で人気のインドラヤニという品種を用いたポット実験で、その効果が実証された。しかし、現状では、このメタノトロフは増殖スピードが遅いため、大規模な培養が難しく、メタン緩和やバイオテクノロジー用途への活用が限られている。今後、培養条件の改善や大規模な栽培技術の開発が、この生物のさらなる応用を促進する可能性がある。
サイエンスポータルアジアパシフィック編集部