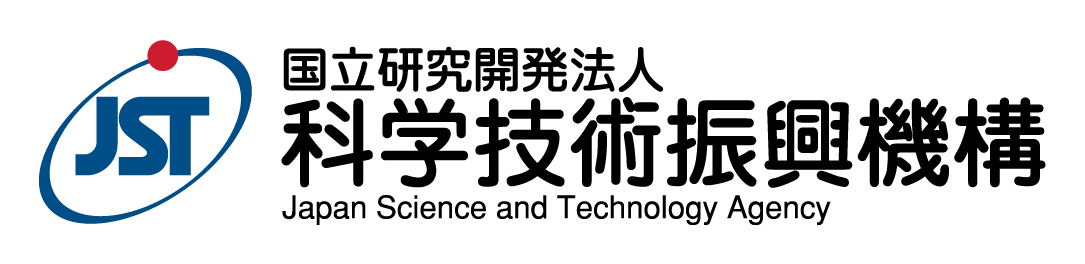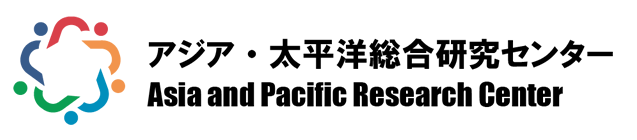腸内定着の口腔細菌がパーキンソン病を引き起こす可能性 韓国POSTECH
韓国の浦項工科大学校(POSTECH)は9月22日、腸内に定着した口腔細菌が代謝物を介して脳内の神経細胞に影響を与え、パーキンソン病を引き起こす可能性を突き止めたと発表した。研究成果は学術誌Nature Communicationsに掲載された。
POSTECH生命科学科のアラ・コー(Ara Koh)教授と博士課程のパク・ヒョンジ(Hyunji Park)氏、成均館大学校医学部のイ・ユンジョン(Yunjong Lee)教授と博士課程のチョン・ジウォン(Jiwon Cheon)氏が研究を主導し、ソウル大学校医学部のキム・ハンジュン(Han-Joon Kim)教授との共同で行われた。研究チームは、腸内に侵入した口腔細菌が産生する代謝物が、パーキンソン病の発症を促すメカニズムを解明した。
解析の結果、虫歯の原因菌として知られるストレプトコッカス・ミュータンス(Streptococcus mutans)が、パーキンソン病患者の腸内で増殖していることが分かった。この細菌はウロカン酸還元酵素(UrdA)を産生し、その過程で生成される代謝物イミダゾールプロピオン酸(ImP)が血中や脳内に高濃度で存在していた。ImPは全身循環を通じて脳に到達し、ドーパミン作動性ニューロンの減少を引き起こす可能性が示された。
マウスの実験では、ストレプトコッカス・ミュータンスを腸内に導入したり、UrdAを発現させた大腸菌を投与したところ、血液および脳内のImP濃度が上昇した。さらに、神経炎症の活性化、疾患進行の中心となるタンパク質であるα-シヌクレインの凝集、運動機能障害など、パーキンソン病特有の症状が確認された。
これらの変化は、細胞内シグナル伝達複合体mTORC1の活性化に依存していた。mTORC1阻害剤を投与したマウスでは、神経炎症やニューロン喪失、α-シヌクレイン凝集、運動障害がいずれも軽減した。研究チームは、口腔腸内マイクロバイオームとその代謝物を標的とすることで、パーキンソン病治療の新しい戦略が見出せる可能性を指摘している。
コー教授は「腸内に定着した口腔細菌が脳に作用し、パーキンソン病を引き起こす仕組みを初めて明らかにしました。この成果は、腸内細菌叢を標的とした新しい治療の方向性を示すものです」と語った。

(出典:POSTECH)
サイエンスポータルアジアパシフィック編集部