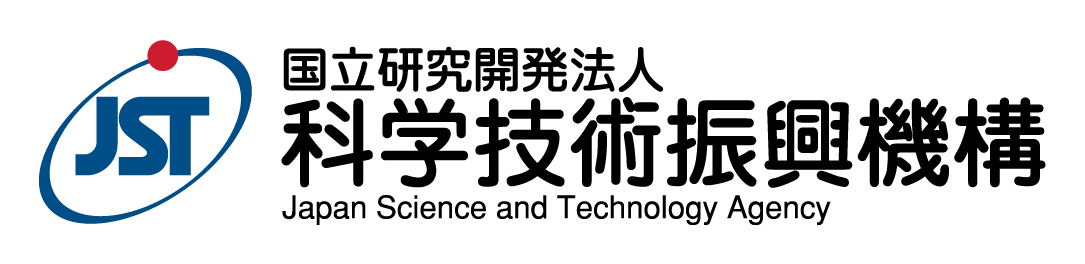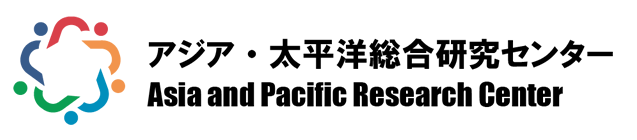初期宇宙の金属量が少ない銀河でも大質量連星を形成 豪モナシュ大学
オーストラリアのモナシュ大学(Monash University)は9月3日、初期宇宙の金属量が少ない環境においても大質量星が近接連星系で形成される確率は現代と同程度であることを明らかにしたと発表した。研究成果は学術誌Nature Astronomyに掲載された。
本研究は、欧州南天天文台の超大型望遠鏡を用いて、小マゼラン雲に存在するO型星139個を対象に行われた。小マゼラン雲は太陽の金属量の5分の1しか持たない矮小銀河であり、研究チームはその環境での恒星形成の特徴を調査した。従来の観測では、金属量の少ない環境では低質量星が連星を形成しやすいとされてきたが、本研究はそれに異議を唱える結果を示した。
天文学における金属量とは、水素とヘリウム以外の元素の割合を指す。金属量は恒星の寿命や進化、さらには連星の相互作用に大きな影響を与える。宇宙初期には重元素がほとんど存在しなかったため、金属量の少ない銀河を観測することは初期宇宙における星や連星形成を理解する手がかりとなる。
調査の結果、観測対象のO型星の約70%が近接連星を構成しており、そのうちの3分の2は生涯のいずれかの段階で伴星と相互作用することが判明した。こうした相互作用は超新星爆発やブラックホール、中性子星合体といった劇的な現象を引き起こし、重力波の発生源となることが多い。
モナシュ大学物理学・天文学部およびARC重力波発見研究拠点(OzGrav)のイリヤ・マンデル(Ilya Mandel)教授は「我々の分析では、小マゼラン雲のような金属量の少ない銀河においても大質量星の連星割合に有意な変化は見られません。これは大質量連星の形成が、初期宇宙においても恒星形成の基本的特徴であることを示しています」と述べた。さらに「連星相互作用はブラックホールや中性子星の衝突、重力波放出につながる重要な経路です。こうした連星がどの環境でもどの程度存在するかを理解することは、重力波事象の検出頻度を予測する上で不可欠です」と説明した。
サイエンスポータルアジアパシフィック編集部