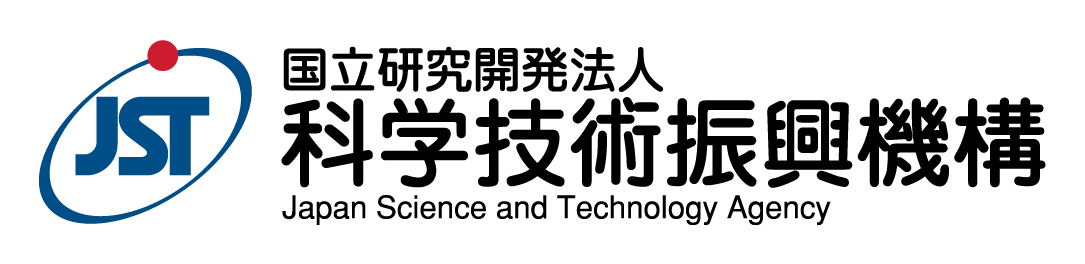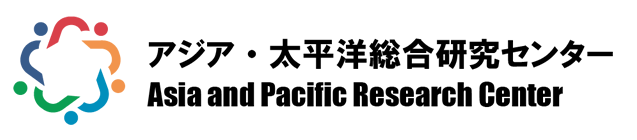防災関連の実験施設とデータを生かし、国内外の頭脳循環を促進:防災科学技術研究所(NIED)寶馨理事長に聞く
2023年9月27日 聞き手 科学技術振興機構(JST)参事役(国際戦略担当) 樋口 義広
国際頭脳循環シリーズの今回のインタビューでは、防災科学技術研究所(NIED)の寶馨(たからかおる)理事長に話を伺った。

防災科学技術研究所(NIED)寶 馨(たから かおる)理事長
国立研究開発法人として共創で日本社会の防災力の強化に貢献する
── 防災科学技術研究所(NIED)が設立60周年という節目を迎える今年4月に理事長に就任されました
私はこれまで大学での仕事がずっと長かった。京都大学工学部の助手、岐阜大学を経て、1994年に京都大学防災研究所に着任した。以来30年近くに亘って防災に関わってきた。たくさんの国際プロジェクトに参画し、国際頭脳循環の一環として、研究者の長期海外派遣も行ってきた。大学の付置研究所として、また大学の一教員という立場で、比較的自由にできたところもあった。
国立研究開発法人であるNIEDは、防災関連で唯一のナショナルセンター的な位置付けのところだ。もともと国家公務員になって、国のために尽くしたいという個人的な思いがあったので、やりがいのある、よいポジションに就けてもらったと思っている。

防災科学技術研究所(NIED)正門(提供:NIED広報)
── ちょうど今年度から新しい中長期目標・計画も始まりました。NIED全体の現状、その中で新理事長として特に力を入れている点などについて伺います
NIEDとして国の防災に取り組むにあたり、オールハザード、オールフェーズで研究を進めることを目標に置いている。オールハザードとは、あらゆる災害に対応すること。オールフェーズとは、予測、予防から、応急対応、復旧、復興まで、さまざまなフェーズを全て考えることだ。そのためには理学や工学だけでなく社会科学等もいろいろと導入して考えなければいけない。

地震観測網模型:観測点が日本全土をカバーしていることが分かる
日本には、陸地と海底を含め、約2,000箇所の観測点からなる地震観測網が設けられており、それによって緊急地震速報もできるようになった。海底のS-net(日本海溝海底地震津波観測網)に加え、N-net(南海トラフ海底地震津波観測網)が今年から来年にかけて2年間で整備される。N-netでは、南海トラフについて、高知沖から宮崎沖まで36点の観測センサーを設置する。このような海底ネットワークができると、陸上だけでしか観測していなかった場合に比べて、20秒早く地震が感知でき、20分早く津波が予測できるようになる。このような基盤的な観測は、阪神淡路大震災以降ずっと整備し続けてきたもので、まだ整備途上だが、すでに実際に緊急地震速報で使われている。これら全国の陸域から海域までを網羅する複数の観測網を統合運用するのが「陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS:Monitoring of Waves on Land and Seafloor)」である。このような重要な基盤的な活動を引き続き積極的に行っていく。
NIEDはいくつもの世界トップクラスの大型実験装置を持っている。例えば兵庫県にある実大三次元震動破壊実験施設「E-ディフェンス」は、三次元の方向から揺れを与えて大型構造物の震動破壊を実験できる世界一の施設だ。つくば本部の敷地内にある大型降雨実験施設は、実際の雨にかなり近いような雨を降らせて様々な実験を行うことができる。また、新潟と新庄にある雪氷の実験施設は、天然に近い結晶形の雪を降らせる装置や風洞装置などを備えており、雪氷に関する基礎研究や、雪氷災害の発生プロセスとその対策に関する最先端の研究を行っている。
こうした実験施設を活用して、観測実験に基づく世界トップクラスの基盤的な研究を推進していく。観測実験データを使って、今よく言われるデジタルツイン、すなわち現実世界にそっくりな仮想世界を双子として作り、いろいろなシミュレーションを実施できる。観測実験を行って、モデル化し、シミュレーションを行って、予測計算をして、あるいはシナリオ分析して、研究成果を出していく。

NIED大型降雨実験施設の降雨実験風景
これらの研究成果は、単に研究論文として出すだけではなく、それを使いやすい情報プロダクツとして公開する。ユーザーがそれに基づいて実際にアクションを起こすことで、研究成果が社会実装につながる流れをさらに推進していきたい。
その過程で、いろいろなステークホルダーと積極的に協力していく。すでに多くの大学と研究協力しているし、防災関係だけでなく、例えばつくばにある環境研究所や土木研究所、建築研究所、農業環境研究所、森林総合研究所など、様々な機関・組織とこれまで以上に連携し、共創していく。競い争う「競争」ではなく、「共に創る」という共創である。共創の流れをさらに推進していきたい。
── 「みんなで創るレジリエントな社会」というのは、貴理事長が就任挨拶の中で述べた言葉ですね

NIEDのロゴ:「生きる、を支える科学技術」(提供:NIED広報)
そうだ。NIEDのロゴの上には「生きる、を支える科学技術」と書かれている。「生きる、を支える」をどう実現していくのかを考えるときに、共創という言葉が出てくる。これを「みんなで創る」という言葉に置き換えてみた。「みんな」というのは、NIEDスタッフ全員という意味と、研究所外の様々なステークホルダーと一緒にという二通りの意味がある。このような共創をきちんと行って、情報プロダクツの形で社会に実装し、国や社会の防災力を高めていくという展開を目指していきたい。
── そのような展開の中で、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、やはり重要なテーマとなるでしょうか
その通りだ。1990年代の終わり頃から、「小さな政府」への流れが出てきている。政府としてインフラなど大きな事業はできないが、その代わり情報公開法を通じて国民に必要な行政情報は積極的に提供するので、情報を取りに来て、自分で自分を守ってください、できるだけ自己責任でやってくださいということである。
ただ、日本が「超超高齢社会」になっている中で、「自分を助けなさい」と言っても無理がある。近年は「自助、互助、共助、公助」と言われているが、自助だけでなく、お互いから助け合う互助も大事になっている。共助は、地方自治体レベルの公助という考え方もあるが、もう少し社会的なルールに基づいて、たとえば保険なども含めて助け合うのが共助である。それよりも、さらにパーソナルなレベルでは互助だ。
今、世の中の潮流としては、国や地方自治体の公助はあまり多くを期待できない。自分たちで自分の身を守らないといけない。そのためには、やはり行政庁が公開してくれる情報をうまく取得する必要がある。ところが、出てくる情報がいいかげんだと、人々は適切な行動が取れない。そういった意味で、やっぱり防災情報を適時、的確、適切に出していくことが重要になってくる。今言われている防災DXや防災デジタルツインなどを通じて、国民に必要な防災情報をあまねく、広く、公平に伝える必要がある。情報処理に長けた人だけが得をするような社会にしてはいけない。年配の方でも、障害のある方でも、子どもでも防災情報が広く伝わって、何をしたらいいか分かるような情報を提供しなければいけない。単に川の水位が何メートルになったとか、雨量がいくらであるとか、震度がいくらだったとかといったことではなく、何をしたらいいのかが分かるような情報をきちんと出していかなければならない。
小さな政府という流れの下にある情報化社会というのは、基本的に個人がしっかりと情報を取って自分の命と身を守るという世界であるが、それをうまく機能させる仕組みが防災DXや防災デジタルツインなどの概念だと思う。
防災は安全保障にも関連する
── 防災が国家の安全やセキュリティと関連するようなことはあるでしょうか
例えば、国境を跨いで流れる川の上流にダムがあるような場合、事故や災害によるそのダムの安全が問題となる。先般、ウクライナのダムが破壊されて洪水になった。誰が破壊したのかは分からないが、結局、防災の話は国家安全保障にもつながる。NIEDの地震や津波の観測網は、国防にも、水産業を守るためにも使えるはずだ。
国も安全保障を高めたいと考えており、我々も、防災だからといって防災にとどまるのではなく、安全保障の強化に活用することも考えていく必要がある。国立研究開発法人として、大学が多少なりとも躊躇するようなことも、積極的に取り組んでいく必要があると思っている。
研究の社会実装、創業・スタートアップとの関係について
── 研究成果の社会実装という観点からの創業やスタートアップといった方向性は、防災分野にどのように関連してくるでしょうか
やはり企業の皆さんも、自分のところの防災は考えていると思う。企業として地域貢献、社会的な責任、CSRといったところも考えながら、企業が自分の防災と関連する地域全体の安全を考えることはあると思う。
そうした安全を考えるときに、たとえば電力・ガス会社や鉄道会社も地震計を持っているし、NIEDもたくさんの地震計をもっている。そういったものをリンクさせて、地震観測ネットワークのおかげで企業にもメリットがあるといった方向に持っていければよいと思う。実際に、データ利活用協議会を過去5年ほどやって、71の企業・団体がその協議会に入ってデータの共有を得ていた。
国際交流、研究環境の国際化について
── 国際化や国際頭脳循環というテーマの位置付けと重要性、NIEDとしてどのように取り組んでいるかについて伺います
NIEDとして職員を海外のどのようなところに派遣してきたかを調べたところ、中長期の在外研究員制度で派遣したのは、平成14年からは17人だった。派遣先は、米、英、カナダ、ドイツ、ニュージーランド、イタリア、フィンランド等の大学や研究所で、結構いいところへ行っている。フィンランドに行った人は、違う環境で考えてみたいということであえて選んだと言っていた。派遣した人の中には、日本に戻ってきた後、京大、大阪府立大、神戸大、筑波大などで活躍している人もいる。NIED から海外に出て、戻ってきて国内の他のところに行くという循環がある。NIEDでも、海外経験者は皆、所内で主力になっており、頼もしい。ただ、近年、中長期の在外研究員の制度が止まっているのは気になっており、これを復活させたいと思う。
また、ArcGISという空間情報を重ね合わせることができる地理情報システムソフトを出している米ESRI社と協定を結んで、NIEDからインターンを受け入れてもらっている。過去3回、それぞれ2~3カ月ほど、有望な職員を研修に行かせた。ESRI社は世界をリードするGISの会社なので、そこへ乗り込んで先方の職員と一緒に働いて、システムを使いながら、いい経験をしてきた。今年7月にサンディエゴで開かれたユーザー大会に私も参加し、社長に今後もNIEDからインターンを受け入れてくれるようお願いしてきた。
NIEDの研究職は今、非常勤も含めて170人ほどで、うち外国人研究者は、中国系やコロンビア、ベネズエラ、ネパール、韓国など6人である。このほかに、防災問題に関心を持つ国が増えていることもあり、トルコ、韓国、イタリア、ベルー、インド、米国等から数ヶ月程度の短期でNIEDに勉強に来た外国研究者もいる。また、JSTがJICAと共同で実施しているSATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)の防災分野での共同研究の関連で、若手の外国人研究者がNIEDや日本の他の研究所に来ることもある。具体的には、クロアチアからポスドクを受け入れたことがある。
実はSATREPSが2008年に始まる前に、「防災分野をつくって公募があるだろうか」と尋ねられたが、私は、絶対にあると答えた。すでに33件の防災分野のプロジェクトが実施されている。私は、この3月までずっとSATREPSの研究主幹を務めてきた。推進委員と評価委員の方は引き続き今もやっている。
海外研究者に一番アピールしたいのは、NIEDにしかない研究施設や設備である。世界一と言っていいE-ディフェンスや大型降雨装置、雪氷防災実験棟、日本全体をカバーする地震や津波の観測網データも、この研究所にいれば容易に使える。こうした研究インフラは基本的に国際的に開放しているので、これが国際人材を引きつける求心力になればよいと思う。他方、いくらアイデアがあっても、こうした実験装置を実際に動かすにはお金がなければできない。たとえば、E-ディフェンスのような震度台を動かす実験は、その上に実物大の建物を建てて、震度台を動かすのに何千万円級の予算が必要になる。
また、NIEDの雪氷研究者は、スイスやノルウェーなどと先端的な研究を行っている。雪の観測の歴史的な記録として、長岡と新庄のNIEDのデータがWMO(世界気象機関)に登録されている。日本のデータとしては、この2点だけである。米ESRI社とはGISについて協定を結んでおり、台湾のNCDR(國家災害防救科技中心)とも協定を結んでいる。

寶馨NIED理事長:国内外の頭脳循環をうまくつなげることが重要
日本には有能な外国人材を受け入れて活用する仕組みが必要
── 日本社会が少子高齢化で活力を失いつつある中で、競争力と活力を維持、強化するためには、他の施策と共に、外国の人材を適切な形で活用していく必要があると思います。これは、研究分野に限らず、日本社会全体のテーマです。日本社会が国際化という課題に対応していくときに、どのような点が重要になってくるとお考えでしょうか
日本に来た外国人で、日本を好きになって帰国する人は結構多い。できれば日本に定住して日本で暮らしたいと思っている人もいる。実際に京大で自分のところに来てポスドクまでなった女性留学生がすごく日本が好きで、できたら日本に定住して研究を続けたいと希望したが、実現できなかった。
優れた能力があり、日本国籍まで取りたいというくらい日本を愛している外国人材や、そこそこの能力でも日本の社会でうまく暮らしていける外国人であれば、社会全体の力を上げるために、受け入れた方がよいと思う。そういう海外人材がうまく日本社会に飛び込めるような仕組みが必要だ。しかし、まだ日本社会の閉鎖的なところや、アカデミズムや企業でポストがないといった問題がある。外国人を受け入れる企業も増えてきたが、まだ消極的なところも結構ある。一時期働いてくれるのはいいけども、将来的に幹部、あわよくば社長までなれるかというと、まだそこまではできないという感じがある。
外国から日本に来る学生や研究者を見ていると、日本人はもっと勉強しないといけないと思う。研究室でも、日本人は早くさっさと帰ってしまうが、中国人や東南アジアの留学生たちは遅くまで勉強している。修士レベルで来た人はドクターを目指して一生懸命やっている。どうして日本人学生はもっと頑張らないのかと思う。
── 日本人研究者が国際頭脳循環に組み込まれるには、どうすればよいでしょうか
国際頭脳循環のプログラムを作っても、修士の間に短期で行かせてもらうならともかく、ドクターまで行って海外へ1年も2年も行きたい人はあまりいない。就職ともうまく連動させて海外派遣できるとよいと思う。学生もしくは若手研究者が海外に行って、2年程度でいい成果を上げて帰ってきたときに、ちゃんとポストがあるという状態にしてあげればよい。
また、大学は人を外に出すよりは、自前で人材を抱えたがる傾向がある。研究プロジェクトのスタイルも、3年や5年の短期のプロジェクトの成果主義なので、教授としては准教授がいてくれて、そのプロジェクトをしっかりとやってくれる方が助かる。准教授や助教をプロジェクトに使ってしまっているところが原因かもしれない。
私自身は、自分の助手で取った学生の例を挙げると、学部の時に海外現場(インドネシア)へ、修士の時はカナダに8カ月、さらにドクターまで上げて、ドクターの途中で助手に採用して、すぐ米国の大学に2年行かせたことがある。帰国後、国内の研究所に5年間行かせて、また自分のところに戻して、最終的に准教授にした。今年3月には教授に昇進した。まさによい頭脳循環ができたと思っている。こうした頭脳循環の例は他にもあると思うので、好事例を集めて共有するようにしたらよいかもしれない。そういう事例があるというのは、意外と共有されていないのではないか。頭脳循環プログラムも、海外派遣から帰ってきて、報告を出しておしまいということでなく、その後についてもちゃんとフォローアップが必要だと思う。
今後、大学ファンドで大学にたくさんの研究費がいくようになると、若手が全部大学の方に行ってしまい、国立研究開発法人に来ないのではないかと少し心配している。NIEDとしては、いろいろな大学とよい関係を結んでいるので、もしも就職先やポスドクの行き先として必要ということであれば、ドクターでもポスドクでも取って、こちらでトレーニングをして、またどこかへ行ってもらうか、あるいは元のところに戻ってもらうなどできると思う。NIEDの優秀な人材がどこかの教授になってくれてもいいだろう。
こうした国内の頭脳循環が、海外経験の機会ともうまくかみ合うようにする必要がある。国内と国際的な頭脳循環をうまくつなげることが重要だと思う。

NIED寶馨理事長(右)と聞き手の樋口義広・JST参事役(国際戦略担当)
聞き手:樋口義広・JST参事役(国際戦略担当)
インタビューは、2023年7月19日、つくば市のNIEDにて実施
(編集:客観日本編集長 曹暉)

寶 馨(たから かおる):
国立研究開発法人防災科学技術研究所(NIED)理事長
1979年3月京都大学工学部卒業、1981年3月京都大学大学院工学研究科修士課程修了、1990年1月京都大学大学院博士課程修了、工学博士。
1990年岐阜大学工学部助教授。1994年京都大学防災研究所助教授、1998年同研究所教授。豪雨洪水災害、土砂災害等に関する研究を長年にわたって行った。また、2014年4月〜2023年3月までSATREPS 研究主幹を務めて国際共同研究を推進。2023年4月より現職。日本高等学校野球連盟の会長も務めている。
<NIED概要>
国立研究開発法人防災科学技術研究所(NIED)
「防災科学技術を向上させることで災害に強い社会を実現する」という基本目標のもと、幅広い研究が行われている。災害を予測し、災害を未然に防止し、被害の拡大を食い止め、災害からの復旧・復興を実現する科学技術を指している。
NIEDホームページ: https://www.bosai.go.jp/
【国際頭脳循環の重要性と日本の取り組み】
国際頭脳循環の強化は、活力ある研究開発のための必須条件である。日本としても、グローバルな「知」の交流促進を図り、研究・イノベーション力を強化する必要があるが、そのためには、研究環境の国際化を進めるとともに、国際人材交流を推進し、国際的な頭脳循環のネットワークに日本がしっかり組み込まれていくことが重要である。
本特集では、関係者へのインタビューを通じて、卓越した研究成果を創出するための国際頭脳循環の促進に向けた日本の研究現場における取り組みの現状と課題を紹介するとともに、グローバル研究者を引きつけるための鍵となる日本の研究環境の魅力等を発信していく。