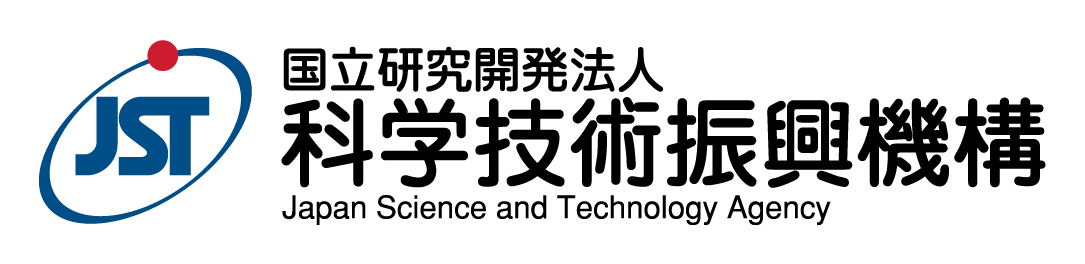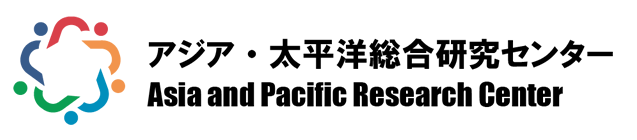自分が成長した日本で放射性医薬品の研究開発と改良に邁進、技術の伝承にも貢献:量子科学技術研究開発機構(QST)張明栄部長に聞く
2023年10月24日 聞き手 科学技術振興機構(JST) 元参事役(国際戦略担当) 樋口 義広
国際頭脳循環シリーズの今回のインタビューでは、量子科学技術研究開発機構(QST)の張明栄部長に話を伺った。

量子科学技術研究開発機構(QST)量子医科学研究所 先進核医学基盤研究部の張明栄(Zhang Ming-Rong)部長
中国の大学を卒業後、日本留学、民間企業を経てQSTへ
量子科学技術研究開発機構(QST)量子医科学研究所 先進核医学基盤研究部の張明栄部長は中国江蘇省揚州市の出身。南京市にある中国薬科大学の薬学部を卒業後、1986年に中国政府の国費留学生として岡山大学に留学し、薬学専攻の修士、博士号を取得した。その後、民間企業に約4年半務め、1998年に放射線医学総合研究所(当時、2016年にQSTに統合)のポスドクに就いた。
張部長の出身地の揚州は、8世紀に日本に渡った唐の鑑真和上の出身地。張部長の実家からわずか5キロ離れたところに鑑真のお寺があり、幼少時から「鑑真東渡」の物語や鑑真が奈良に開いた唐招提寺のことも知っていた。中国薬科大学は当時中国で数少ない単科大学で、日本の岐阜薬科大学と交流があり、日本の教授と話す機会もあったため、日本に行って勉強することに関心を持った。大学卒業の年に、中国政府の日本派遣留学制度に応募し、合格した。留学前の8カ月間、日本語を集中的に学んだ。「日本への留学は当時の自分にとっては最良の選択でした。生活レベルはもちろん日本の方が高かったし、学問的にも、有機化学の分野をはじめとして、日本は先端を走っていました」と張部長は振り返る。
岡山大学では、修士も博士も薬学を専攻した。「最初は日本語と専門用語が大変でしたが、なんとか頑張りました。日本のいいところは、大学の先生が根気強く、人を育てるということです。目の前の成果より、自分の学生を育成することを大事にする先生が多かったと思います。いわゆる「恩師」と呼ばれるような先生です。私も、とにかく学会で発表するというミッションを与えられ、それを通じて日本語の訓練をずっと繰り返しました。学会の発表が終わったら、自分の日本語能力はワンランク上がったと実感しました。このような日本の堅実な人材育成法を、今でも私は大いに評価しています」
博士号を取った後、張部長は民間の健康食品企業に就職し、天然物を抽出する仕事に携わった。もっと自分の化学の知識を活かせるよう、仕事を変えることを考えていた1998年、薬学専門誌に掲載されたJSTのCREST (戦略的創造研究推進事業)の求人広告が目に入った。放射線医学総合研究所(当時)の須原哲也氏(現QST量子生命・医学部門長)が率いる「脳を守る」研究で、張部長はこのプログラムのポスドクに応募した。「放射性医薬品を人間に使って、すぐに役に立つこと、自分が研究した成果を使って、どういう結果が出るかがすぐ分かることが、私にとっては大きな魅力でした」と張部長は語った。張部長の放射性医薬品開発への取り組みはこの時から始まった。
最初の2年間のポスドク後、加速器(サイクロトロン)を運転する役務職員として働き、任期制職員として採用された。その後、2007年には定年制職員となり、チームリーダー、グループリーダーを経て、先進核医学基盤研究部の部長に昇進し、現在、約60名の研究者やスタッフを束ねるリーダーを務める。「優秀なスタッフがいてこその自分だと思っています。我々のところには、優秀な研究者、技術者など、いろいろな人がいます。それぞれ個性があるので、それを尊重しながら大事にやっていかなければなりません。いろいろな考え方があるにせよ、薬を最終的に仕上げて臨床に持って行くというミッションを我々は共有しています」
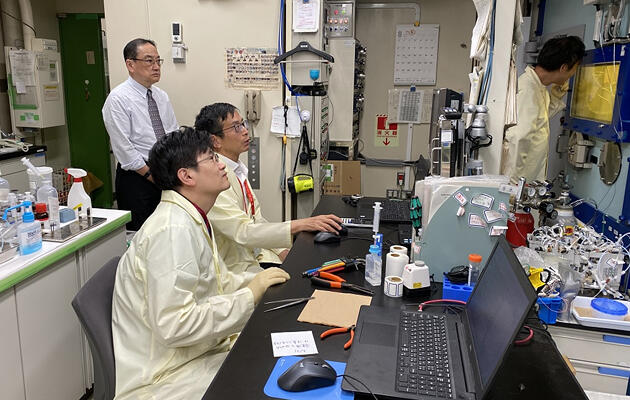
PET薬品の自動合成装置を操作する張部長とスタッフ
PET薬品の研究開発では世界トップ
張部長は放射性医薬品を研究開発している。QSTにおける放射性医薬品は診断と治療、大きく分けて2種類ある。一つは、がんなどの所在を明確にするイメージング技術であるPET(陽電子放出断層画像法:Positron Emission Tomography)に使う放射性医薬品。たとえば、認知症の診断については、放射性核種でラベリングした化合物を患者に注射すると、その化合物が認知症の原因とされるβアミロイドと結合して集まるので、PETの画像でその場所を確認することができる。
もう一つは放射線を利用したがんの治療薬で、薬を人体に注射して、人体の内部からがんを直接照射して治療する。張部長は、元々はPET薬品の開発だけに携わっていたが、後に治療薬も研究するようになったという。
「PETの場合、我々の施設では実際に臨床で使用可能な薬剤は120種類以上あり、7割が脳に関するものです。PETの研究対象は時代とともに変わってきています。例えば1980年代はドーパミン、統合失調症、そして1990年代は睡眠や不安などでした。2000年代に入ると認知症となり、アルツハイマーや、最近では非アルツハイマーの認知症が対象になりました。2000年代に共同研究者とともに開発した薬は、特許を取り、ドイツ企業にその特許を売却しました。最終的には臨床には至りませんでしたが、自分にとってはこれが初めて社会実装できた薬でした。我々のグループが開発した薬で、臨床まで持っていけたのは大体10種類です。今は、脳機能の医師と共同で開発した認知症の診断薬の臨床試験をしています」と張部長は自分の研究成果を振り返った。
QSTが開発したPET薬品及び製造技術は世界トップクラスだ。現在まで、128種の放射性医薬品を製造し、臨床研究に提供してきた。日本に続く米国やスウェーデンの施設では30~40種類しかもっておらず、この差は非常に大きい。1979年に放射線医学総合研究所(当時)で日本最初のPET臨床研究が行われ、現在ではアルツハイマー型認知症だけではなく、非アルツハイマー型認知症にも対応できる薬も開発している。これは世界でも他に例を見ない薬で、実際に特許も取得している。現在この薬は、日本、中国、米国などでそれぞれ臨床試験の段階に入っている。
最近、認知症の治療薬の開発が大きな話題になっているが、PET薬品は認知症の治療においても非常に重要な役割を果たしている。認知症治療薬を患者に投与してよいかどうかは、PETで事前に判別する場合があるからである。治療薬をどの段階で患者に投与するかによって、治療結果も大きく違ってくる。早くに投与すれば効果が出るが、ある一定の時期を過ぎてしまうと、もう効果は発揮されない。PET薬品を使えば、βアミロイドなどがどこにどれぐらいたまっているか、病状の進行段階が瞭然となるため、診断薬としての評価は高い。今後、認知症のPET診断は保険の対象になることも期待されている。
また、PETは一般的な医薬品開発のツールとしても活用されている。例えば、ある薬の開発において、製薬会社が臨床に持っていく前に、この薬は体の中でどのように動くか、頭に行くのか、腎臓から排出されるのか等について、PETを使って効率的かつ確実に観察することによって、臨床研究をスムースに進めることができる。すでに製薬会社と様々な共同研究が行われているという。
張部長は、二つの点についてPET薬品の改善にも取り組んでいるという。「一つは、薬の製造方法の改善です。通常の薬であれば、製造に時間をかけても構わないし、放射能も気にせずに済みますが、放射性医薬品の場合は、いかに短時間で効率的に、かつ被ばくを少なくしてつくるかが重要な開発テーマになります」。PET薬品に使われる放射性物質の半減期は数時間と短く作り置きができないため、検査直前に短時間で調製する必要がある。「もう一つは、作った薬品をさらに改善していくことです。動物でうまくいっても、臨床では必ずしもそうとは限りません。うまくいかない時には、薬品の化学構造を変える必要も出てきます。たとえば、薬が脳にうまく入らない場合には、もう少し油の構造を持たせるなどの改良を図ります」
一方、放射性医薬品を用いてがんを治療する標的アイソトープ治療については、現状ではドイツや米国の方が日本よりも進んでいるという。日本では、施設によって、1日に扱える放射線の量が厳しく制限されていて治療に使いにくいという事情がある。「臨床における(放射性)治療薬の利用については、日本はやや遅れをとっていますが、標的アイソトープ治療に用いる核種の中で今最も有力なアクチニウム製造については、日本は独自の路線を走っています。商業化も検討されており、世界中から注目されています。小型サイクロトロンからアクチニウムを製造する技術については世界トップと言ってよいと思います」
研究成果の事業化について、張部長自身はベンチャーに参加していないが、彼らが開発した有望なシーズにベンチャー企業が投資した例があるという。ベンチャー企業が特許の実施権を優先的に取得するとともに、研究費を提供するという仕組みである。
研究環境の国際化と国際頭脳循環について
張部長は、外国人材を受け入れるという観点からの「国際化」について、QSTは日本の一般社会よりも進んでいるし、特に彼が率いる先進核医学基盤研究部は、QSTの中でも特に国際色が豊かなところだと言う。「我々の研究所はIAEAの教育拠点になっているので、定期的にIAEAから人を受け入れています。自分の部署だけでも、長くて1年、短くて1週間、さまざまな形で年間10名程度が出たり入ったりしています。このように、QSTでは人員の国際的な出入りが非常に多いと思います」と張部長は述べる。「我々の部には、中国、イラン、カンボジアなど、いろいろな国の出身者がいます。特に東南アジアからの人が多く、これは東南アジアにおける日本のプレゼンスの大きさを感じさせます。こうした人材が自国に戻って活躍すれば、日本、そして指導にあたった私も評価されることになります。これはとても嬉しいことです」
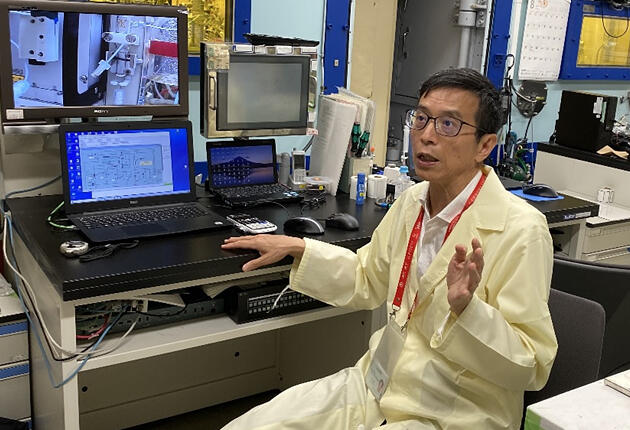
「薬品の研究開発は多くの技術者によって支えられている」と張明栄部長は述べる
日本には学問に対する尊厳が残っているので、じっくり研究できる
「自分が成長した場所、すなわち日本が私のすみかです。最初は何一つ分かりませんでしたが、日本に適応してきました。学問をしっかりと真面目にやるのであれば、やはり日本はよい選択肢の1つだと思います。日本社会も変化したとは言え、きちんと学ぶという環境がまだあり、じっくり研究することができます。米国も、中国も、社会の変化があまりにも早過ぎ、環境に適応できない若者がたくさんいて、いろいろな社会の問題やひずみが生じています。日本の場合は、少しずつ変わってはいるけれども、学問に対する尊厳や尊敬はまだ残っています。もちろん、それぞれの場所には長所も短所もあります。日本の場合、じっくり研究ができますが、他方、世界の速さになかなか適用できないという問題があるかもしれません」
さらなる国際化に向けた課題
日本の国際化や国際頭脳循環をさらに促進することに関して、張部長はいくつかの問題点を指摘した。
一つは、日本から外国に出ていく人が少ないことである。「研究所内でも、毎年外国へ行く人を募集しますが、ほとんど手が挙がりません。私が若い時だったら当然行くと思いますが、今の若い人は、どうしても安定を求めます。日本の生活はあまりに快適で便利で、何も外国に行って苦労することはないという気持ちが強いのでしょう。私の子供も、別に外国に行かなくても日本でちゃんとやっていけると言います。これは成熟した社会の一つの証でもあります。最近ではコロナの影響もあったかもしれません。また、制度的な問題としては、たとえば、任期制の人たちはもともとポジションが不安定で、外に出て戻ってきたら職がどうなるか、皆不安でなかなか外に行けません」と張部長は指摘する。
ちなみに、中国では、海外留学を希望する学生は多く、また、たとえば大学の教職に就くには、3年以上のポスドクの経験が必須であるなど、海外経験がキャリアパスの必要条件になっているという。日本との大きな違いだ。
先にも述べたように、張部長は、外国人の受け入れについては、QSTでもかなりの程度進めているとしつつも、日本全体で見た場合、まだ困難や課題があると言う。特に、日本の大学等のテニュア制度は外国人にとってはハードルが高いという。また、言葉や住まいの問題など、外国人が日本で生活する上での困難がまだあるともいう。
研究開発に関連する技術の伝承が自分の使命
今後の見通しについて問われた張部長は、「今のところは日本で仕事を続けていくことを考えている」とした上で、次のように述べた。
「私が今一番大事にしているのは、技術の伝承です。私がいるところは、最先端の研究を支える基盤組織で、研究者だけでなく、職人芸を持った技術者たちに支えられています。先ほど研究室で見てもらったPET薬品の自動合成装置などは、最初は私がパンチングボードをたたいて自分で作っていました。ところが、最近はそういう作業をする人はいなくなり、既製品を使うようになっています。しかし、そうなるとイノベーションはあまり生まれてきません。私は、若い人たちが入ってきた時には、泥臭くてもよいので、パンチングボードを自分でたたいて簡単な合成装置を作って、そこから原理原則を学んだ上で開発に取り組んでいくよう、常に言っています」
「我々の組織を支えているのは技術者で、いわゆる昔の職人が多いのです。彼らがいなくなると技術は失われてしまいます。日本の社会を支えている技術といっても過言ではありません。基本的に研究者の場合は、極端に言えば、ここでなくても別のところに行けますし、彼らが抜けてもこの組織は成り立つかもしれません。しかし、技術者がいなくなると我々の根本的なものがなくなってしまいます。そういった技術を若い人にどのように伝承していけばよいか。このことが、これから私が最も力を入れて取り組んでいかなければならないことだと思っています」
「もちろん、今までやってきた薬をさらに進化させ、製薬会社ともいろいろな話をして、社会に還元することもやらなければなりません。同時に、技術の高度化と効率化を図って、時代と共に歩んでいくことが私に残された役目だと考えています」

QST張明栄部長(右)と聞き手の樋口義広氏
インタビューは2023年8月30日、千葉市稲毛区のQST本部にて実施
聞き手:樋口 義広・JST参事役(当時)
(編集:曹 暉 客観日本編集長)

張 明栄(Zhang Ming-Rong):
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(QST)量子医科学研究所 先進核医学基盤研究部部長
1985年に中国薬科大学を卒業。1986年に中国政府の国費留学生として岡山大学に留学。薬学専攻の修士、博士号を取得。民間企業に約4年半務め、1998年にQSTでポスドクに就いた。2007年にQSTの定年制職員となり、チームリーダー、グループリーダーを経て、現在、先進核医学基盤研究部部長。約60名の研究者やスタッフを束ねるリーダー。
<QST概要>
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(QST)
「量子科学技術等による持続可能な未来社会の実現する」という基本目標のもと、量子技術イノベーション研究、量子医学・医療研究、量子エネルギー研究、量子ビーム研究を中心に研究を推進。日本における量子科学技術研究の中核を担う研究機関である。
QSTホームページ: https://www.qst.go.jp/
【国際頭脳循環の重要性と日本の取り組み】
国際頭脳循環の強化は、活力ある研究開発のための必須条件である。日本としても、グローバルな「知」の交流促進を図り、研究・イノベーション力を強化する必要があるが、そのためには、研究環境の国際化を進めるとともに、国際人材交流を推進し、国際的な頭脳循環のネットワークに日本がしっかり組み込まれていくことが重要である。
本特集では、関係者へのインタビューを通じて、卓越した研究成果を創出するための国際頭脳循環の促進に向けた日本の研究現場における取り組みの現状と課題を紹介するとともに、グローバル研究者を引きつけるための鍵となる日本の研究環境の魅力等を発信していく。