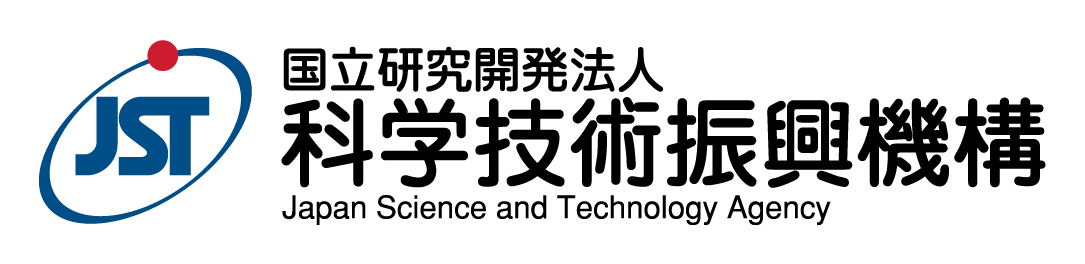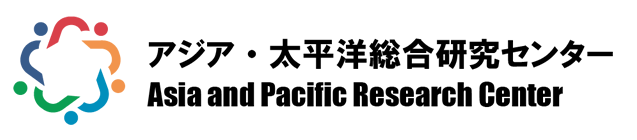「発見の喜びを原動力とする最先端研究を人類の未来につなげる」:理研・五神真理事長に聞く
2023年11月15日 聞き手 科学技術振興機構(JST)元参事役(国際戦略担当)樋口 義広
国際頭脳循環シリーズの今回のインタビューでは、理化学研究所(理研)の五神真理事長に話を伺った。

五神真・理研理事長
理事長に就任後、「2030年ビジョン」を発表
── 昨年、理研の理事長に就任して2030年に向けたビジョンを発表されました。まずこのビジョンや理研全体の現状、理事長として特に注力されている点について伺います
五神:理化学研究所は、1917年に創設された。1914年に始まった第一次世界大戦のなか、医薬品や工業原料の輸入が途絶して困難になり、明治維新以来の先進国からの技術導入による発展の限界も意識され、資源の乏しい日本だからこそ模倣ではなく、独創力をもって産業を興すことが求められた。高峰譲吉博士は渋沢栄一氏に「これからの世界は必ずや機械工業よりもむしろ理化学工業の時代になる」と説き、その基礎づくりとして「純正理化学」の研究所が構想され設立された。科学者が自由に楽しく研究し、自分の考えている問題を超えて研究者仲間と交流することでまた新しいアイデアが生まれていく。それは後に「科学者たちの自由な楽園」と評されたが、そんな素晴らしい研究所をつくろうとすることこそが「理研精神」の源流である。
時代を経て今、理研は何をするのかということが問われている。百年をかけて受け継がれてきた「理研精神」をただ拝んでいれば良いというわけにはいかない。経済的な価値はモノからコトへシフトし、社会経済は20世紀の高度経済成長を支えた資本集約型から知識集約型へパラダイムシフトしている。「理研精神」も現代的に見つめ直し、新しいビジョンを理研が自ら示して行かねばならないと考えた。そこで、新しい行動指針「RIKEN's Vision on the 2030 Horizon」をまとめ、昨年8月に発表した。ここで、知の発見とは胸躍るおもしろいもので、研究とは自らの好奇心を原動力としてやりたいことを集中してやりとげるものだ、ということを強調した。国立研究開発法人として社会に貢献するということを意識しながらも、好奇心をベースにした研究にしっかりと取り組むことが重要だと考えている。
研究者がおもしろい、やってみたいと思うことが、未来の人類が求めることにつながることが大切だ。人類に知恵が足りないために困っている問題を解決に導く、突破口となるような最先端の研究に胸を躍らせながら取り組み、成果を出す。それを通じて社会から信頼され、社会との好循環ができて、日本が世界から尊重され、未来に向けた成長につながる。そうしたことを効果的に進めるための環境づくりと、それを実現するための仕掛けを盛り込んだ。
現在、人類はさまざまな難しい課題に直面している。たとえば地球温暖化への対応やエネルギー問題、社会の分断や格差拡大、これらは手元にある知識だけでは解決できず、新しい知恵が必要になっている。知恵を生み出さない限り解決はないとすれば、その原動力は人材だ。多くの若者が強い好奇心を持って課題に取り組み、それを楽しいことだと感じ、明るい気分でがんばることが重要だ。
実際、最近の世の中を見ると、これまで思いもよらなかったような革新的な知恵や技術が続々と出てきている。COVID-19に対して、mRNAワクチンがごく短期間で開発された。iPS細胞やゲノム編集、量子コンピュータ、生成AIなどをめぐって、まったく思いもよらなかった知見がここ10年、20年で数多く出現してきた。この背景にはやはりデジタル革新DX(デジタル・トランスフォーメーション)がある。さまざまな事象がデジタルデータとして蓄積され、半導体エレクトロニクスやインターネットあるいは人工知能技術などの劇的な進歩により、その巨大なデータを一気に解析し活用することが可能となったからだ。このDXによって従来のリニアモデルの延長上にはない、不連続な変化点、パラダイムシフトが起きる時代になった。そこでは、研究が基礎か応用か、長期か短期かといった旧来の区別はあまり意味がなくなる。自由な発想を起点としながら研究力を高いレベルに引き上げることが、産業や国力の観点からも不可欠になる。最高水準の優れた研究者を集め、切磋琢磨し、シナジー効果を出しながら、新しい知恵を次々生み出す場をつくりたい。これが理研の理事長になったときに思ったことだ。
理事長に着任して最初の1、2カ月で、全研究センターを回って、研究者たちと膝をつき合わせて話をした。だれもが皆、目を輝かせ、自信満々で生き生きと語ってくれ、非常におもしろかった。また、理研には理研白眉制度(2017年創設)という、並外れた能力を持つ若手研究者に、研究室主宰者(チームリーダー)として独立して研究を推進する機会を提供し、国際的な次世代リーダーを養成するプログラムがある。現在このプログラムのもとで研究を行っている10人以上の若手研究者たち全員と面談した。野心的でユニークな人たちばかりで、研究の話に引き込まれた。予定時間の30分を超えて、1時間、1時間半と話し込むことも多く、プログラムがうまくいっていることがわかった。
一方、気になることもあった。昨日あのセンターで聞いた話と、今日このセンターで聞いた話は極めてつながりが深く、データの解析の仕方など、お互いに当然日々議論しているのかと思ったら、実はあまりしていないということが多かった。センターを越えた交流が限定的なのだ。これは大変もったいないと思った。理研にはきわめて優秀な研究者たちがいるので、それを積極的につなぐ仕組みがあればもっと力を発揮できるはずだ。そのような思いのもとで、昨年、TRIP(Transformative Research Innovation Platform of RIKEN platforms)という構想を打ち出した。これは理研の強みである最先端研究プラットフォーム群(スーパーコンピュータ「富岳」、量子コンピュータ、大型放射光施設「SPring-8」、X線自由電子レーザー施設「SACLA」、バイオリソース事業など)を有機的に連携させ、研究分野を超えて新たな知の領域を効果的に生み出す、革新的な研究プラットフォームを築くというものだ。
昨年は、この構想を打ち出し、まずは研究者の反応を見た。そこで、次年度の活動の説明の際に、トップダウンのビジョンであるTRIP構想との関連について説明してもらい、そのために必要な予算を追加配分するという方式を導入した。TRIP構想提示からわずか数ヶ月であったが、理研の研究者の対応は迅速だった。各センターの今年度の予算要求のなかでTRIPと関連づけられた研究は既に50%近くになっていた。海外のアドバイザリー委員会からも斬新なスキームとして注目されており、この構想が求心力を生むことを期待している。現在、来年度に向けて計画をさらに発展深化させようとしている。

理研の新本部棟(埼玉県和光市)

理研の西門入口(同)
アカデミアの力で産業構造を未来型に変革する
── 地球温暖化の問題に関連して、人間はやりすぎたので、成長は止めるべき、もっと抑制して、我慢して、押さえなければいけないという議論があります
五神:そのような議論には違和感がある。時間の流れは不可逆で、戻ることはできない。成長を止めるのではなく、新しい知恵をどんどん出し、成長のあり方そのものを探るなかで解決していくしかない。問題はより明確になっているのだが、何をやればよいかについては、高度経済成長期のもの作りによる成長モデルのように、ロードマップに従って着実に計画を進めればすむといった単純なものでない。価値づくりそのものに取り組むという難しいことをやらなくてはならない。
理研では、基礎科学研究を未来の成長の機会を創る源泉と捉え、そこにまず注力し、それが新たな価値を生み、そこに新しい産業が展開されていくことが重要であると考えている。産学連携的な活動は、創立時からの理研の文化だが、今必要なのは、単に過去の研究成果を既存の産業界に展開するのではなく、日本の産業全体を伸ばしていくために、産業構造を未来型に変えていく。そのためにアカデミアの力を役立てることだ。現在、日本では、未来のための投資先がなかなか見つからない状況になっているが、産業界が未来に挑戦すべくリスクをとって変革していくために、最先端の研究成果をどううまく発展させ使うかという発想が必要だ。国内外の企業トップの方々と交流してみると、海外のCEOはそういう発想を自然に持っている人が多いと感じる。日本にもそういう経営者はいるが、まだ少ない。
新しい知恵を新しい産業につなげるためには、テック系のベンチャーが育つ仕組みをつくることも重要だ。この点も、日本は欧米に比べて遅れている。その理由の1つは、日本のベンチャーキャピタルが早めのリターンを求める傾向にあることだ。小ぶりで早々に上場するのがよいということとなっている。それだと、我慢が勝負のような大ぶりのテックベンチャーは育たない。
私が東大の総長になった2015年当時、東大発ベンチャーは200社くらいだったが、6年の任期が終わるころには500社近くまで増えた。東大キャンパスの周辺は「本郷バレー」と呼ばれた(地形的には「ヒルズ」だが)。理研では、戦略的にフォーカスして、テックベンチャーを生み出すエコシステムを日本につくることに貢献したい。国とも相談しつつ、海外の投資家や企業とも一緒にやっていきたい。鎖国して日本のなかだけでやろうというのであれば成長の機会を失う。海外とは積極的に進めることが重要だ。理研は国立研究開発法人として、大学ではできないところまで積極的に踏み出していく役割を担っている。
一方、国際環境は極めて複雑で微妙な状態になってきている。研究インテグリティのような問題を、国内法令だけでなく、相手国の法令も含めて、きちんと適切に処理するマネージメント力を格段に向上させることが必須になっている。研究者の国際活動を規制するのではなく、研究者が危険にさらされずに国際的な研究活動を活発にできるようにする必要がある。理研のトップ研究者は、すでにかなり太い国際ネットワークを持っており、研究インテグリティに関する機能を組織的に高めることで国際化がさらに推進できるだろう。
優秀な研究人材の獲得
── 優れた研究成果を出すためには国内外の優秀な人材を獲得する必要がありますが、人材獲得競争は今後益々激しくなると思われます
五神:現在は、価値軸が大きくパラダイムシフトしているので、今まで蓄積されてきた知恵のなかでも、「使える/使えない」といった評価が180度逆転する可能性がある。情報科学なども活用しつつ、そうした新たな評価軸を効率よく感知しながら、新たな知恵を足して望ましい価値創造に役立てていきたい。昔だったらビジネスとして駄目な理由が100もあった技術が、今は根本ががらっと変わり、新たなビジネスチャンスが出てきているという話もたくさんある。発見の喜びを生業とする人々にとっては、今ほどエキサイティングな時期はないかもしれない。
そういう意味で、理研は、若い人たちがわくわくしながらおもしろい研究ができる場であると思ってどんどん集まってくるところであるべきである。未来に対して後ろ向きにならず、ポジティブな出口を求め、そこに向かって活動し、最先端を切り拓く拠点でありたい。世界水準での卓越性は必須の前提だ。そういう場所が日本でいくつか用意できれば、日本は国際的に大いに尊敬され、尊重される国になれる。理研の役割もそこにある。そして、理研がそういう場所であるということを、掲げるビジョンとともに、対外的にしっかりと伝えていく。理研の活動をしっかりと見せていくことが重要だ。この点は欧米と比べるとまだ劣っている。また、科学的なことに興味を持つ人の絶対数が少ないという問題もある。
何よりも、理研で研究をやっている人自身が、研究を楽しく進めていることが重要で、理研の「夢のある姿」を伝えていくことが急務だ。そういう発信をどうしていくか、国内外において広報を強化していかなくてはならない。何よりも、ハイレベルな研究をしている、あるいはしたいという人が世界中から集まれるようにしなければならない。そのためには、これからも理研は多くのことを変えなくてはならない。
昨年は、研究者の有期雇用の問題が顕在化したわけだが、有期雇用自体は、世界トップの研究機関として当然備えておかねばならない雇用制度だ。多様なプロジェクトに研究者がそれぞれの専門性を発揮して、期限を定めて集中的に取り組み、時代が求める課題に対し大きな成果を挙げてきた。そこに参加した人びとの多くがその経験を活かし、その後も研究者として活躍されている。しかしそれを信頼ある形で運用していくためには、理研だけにとどまらず、研究者雇用制度全体の安定性を高めていかねばならない。それによってプロジェクトに集中的に参加することが生涯キャリアにとってプラスになるという環境を創っていくのだ。そのような考えで理研における雇用制度の改革を進めている。
さらに、教授ポストを得るまでに何年もかかるなど、大学でのキャリアパスが今の若者にとって非常に厳しく感じられているという課題がある。そこで、理研では若手研究者が自分の発想で自由に研究ができるようなPIポジションを得るための新しい制度(RIKEN Early Career Leaders Program制度)を創設した。
一方で深刻な問題は、現在の理研の研究者の待遇が国際標準に照らして十分に魅力があるとはいえないということだ。急激な円安等もあり、理研の若手研究者ポジションの給与などが明らかに見劣りする状況になった。博士号取得から5年以内の若手研究者を対象にした基礎科学特別研究員制度の給与を数万円引き上げるなど、改善策を急いでいる。
海外から研究者たちを招くときの給与も、今まではかなり均等な査定になっていたが、分野や状況によってケースバイケースなので、評価をきちんとした上で、かなり大胆に弾力化することを進めている。理事長の給与を超えるような人もどんどん雇いたい。そうすることで競争の激しい分野のトップ研究者にも理研に来てもらえればと思っている。制度としては、すでに給与上限は撤廃したので、これをしっかり運用していく。
研究者の流動性と安定性を両立させるには、理研だけでできることには限界がある。日本の研究者雇用制度の全体もグローバルに見て、修正すべきことがたくさんある。研究という現場に見合った労働法制の整備が望まれる。制度を変えることも現場からしっかり提案していかねばならない。また、研究者のジェンダーバランスの是正も急務だ。日本の現在の状況は国際的に見て、「病気」と言われることも多い。危機感をもって、多少強引なことでも進めていかねばならない。まとまった数の女性研究者を採用する仕組みを創るなど、理研で何ができるか検討している。
国際化とは、日本独自の知恵を出すことで世界の知の多様性に貢献すること
── 研究開発の国際化への取り組みについてどのようにお考えでしょうか
五神:まず、何のための国際化かということを考える必要がある。それは、すでにあるグローバルなスタンダードでフラットに競争してランキングの順位を上げて、外の優秀人材を呼び込むというようなことではないと思う。
人類が知的な課題をたくさん抱え、その課題が急速に明確化してきている。それを解決する知恵を生み出す為には、生み出す土壌の多様性が重要だ。私は日本でなければ出せない独自の知恵というものがあると思っている。世界全体の多様な知を支えるポートフォリオというものがあるとすれば、日本が支えるべき独自の領域というものがあるのではないか。それを掘り起こし、もっと積極的に世界展開することができれば、地球全体をよくするために日本が際だった貢献ができるはずだ。そういうものがあれば、それを学びたいという人が世界からやって来る。私は、東大でも「世界の多様性を支える」と話していた。欧米の大学モデルに無理に押し込もうという発想では駄目だということだ。
日本は欧米とは異なるところがたくさんあるが、それは決して悪いことではない。もしかしたらその違いこそが人類全体にとっては大きな強みで、新たな解決策のきっかけになるかもしれない。だから、自分たちが何か違うものをもっているということに自信を持たなければいけない。ヨーロッパをはじめ、世界が多様なものをうまくつなごうと努力しているときに、日本も多様なものを投ずることができる立場にあるという自覚が必要だ。独りよがりでなく、そうした日本の多様性が必要だと外の人たちが思ってくれるような環境をつくる必要がある。
そのためには、人生のなかでかなり早い時期で、グローバルな視点で自己を相対化して、自分が何者かを知ることが必要だ。そのために一番よいのは外に出てみることだ。
理研の国際戦略:世界的な知のネットワークを構築する
五神:日本の独特な文化や学問を世界に浸透させることで人類全体に貢献する、ということの意義がますます大きくなっていると思う。自分の経験でも、いろいろな人が興味をもって集まってくるのは、流行の研究ではなく、やはり他にない独自の研究をやっている場合だ。そうした独自性を積極的に外に見せて、日本だからこそそのような研究ができているということ、そしてそれがおもしろいと思う人が集まってくるような状況を創りたい。そのためには、集まってくる人たちが研究以外の面でもちゃんとサバイブできるよう、しっかり支援しなければならない。配偶者の仕事や子どもの学校等の問題を含め、しかるべく支援していく必要があるだろう 。理研もその点についてはさらに強化する必要がある。
理研として効果的な国際戦略を進めたいと思っているが、それは研究労働力として外国人を集めるというのではなく、日本人を含め、海外を拠点として知をクリエイトするような人を積極的につないで相乗効果を発揮させることにある。理研のキャンパスに来てもらえれば一番よいが、そうでない場合は、リモートでのクロスアポイントメントというような形で契約を結んでリモートで連携できるような海外研究室の数を大きく増やすのが有効ではないかと思っている。
量子コンピュータのように、皆が最先端でしのぎを削っているような分野では、最先端研究者同士が組むことが重要だ。論文を書く前のラボノートの段階で互いに情報を共有でき、リモートであっても、日々議論できるような"常時接続"の関係をつくる必要がある。欧米のトップ研究者はすでにそういう状況で、日本人だけが論文が公表されてから読むというのでは間に合わない。そういう研究者が理研を経由してつながるリモートオフィスのようなものをつくることを次期中長期計画のなかで進めていきたい。そうすることで国際協力も自然な形で進んでいくだろう。競争はもちろん必要だが、最先端の情報を互いに迅速にシェアできることが大事だ。そうした圧倒的に進んだ国際協力の場を理研で実現していくことが、日本全体の研究の国際化にも効果があると考えている。
また、COVID-19によるパンデミックの経験で再確認されたのは、やはり対面での議論がどうしても必要で、そこから生まれる価値は圧倒的に大きいということだ。顔色を見ながら、互いに信頼しつつ、ときには秘密も明かしながら、深い議論をしなければならない。普段はリモートでやるにしても、やはり時間を見つけて互いに行き来することが重要であり、そのためのオフィスは海外にも必要になる。
米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)に設立された理研BNL研究センターは、先般、設立25周年を迎えたが、若い研究人材を育てる国際頭脳循環の拠点として、日米連携で行った科学技術協力事業のなかで最も評価されている例である。同センターからはすごい研究者がたくさん巣立っている。米国では、理研といったときに、この理研BNLが一番目立っているという話も聞く。こういう拠点を起点として、日本で生まれている多様性、世界の多様性を補強するような要素を海外にも積極的に提供していくことが理研の使命の1つだと思う。
理研には、外部の優秀な研究者にとって、時間を費やして話すに足るだけの議論の相手がたくさんいる。そのことを理解してもらい、その価値を活かすために誰に伝えるのが一番良いのかをしっかり見極めるのが理事長の仕事だ。漠然と発信していても意味がない。世界の本当の最優秀層、トップ研究者に、無駄なく確実に響くよう、うまく伝えていくことが必要だ。
欧米で優秀な研究を行った日本の若手研究者が日本に戻ってきた後、爆発的に活躍できていない例がある。何が違うかといえば、人が密集して議論し合っているかといった、日々の議論の質とその密度が足りていない。やはり1人だけでは難しいので、ある種のクリティカルマスが必要だ。その場合、日本人だけでゼロから立ち上げるのではなく、一緒に組みたいと思う海外の人脈をうまくつないでいくことが重要だ。バーチャルでもよいので、海外の大学に理研のラボを置かせてもらったり、若手が常駐できるようにしたり、その先生をクロスアポイントメントで雇ったり等、いろいろ工夫が必要だ。つながることで、相手方に何が起こっているか、論文が出る前に分かるし、彼らが困っていることについて一緒に議論して知恵を掛けあわせられれば、貢献もできる。
これは、そういう人脈がある程度つながっている今のうちに急いでやらないといけない。ただ漠然と「共著論文をふやしましょう」「海外への旅費を出しましょう」といっているだけでは、状況は何も変わらない。優れた外国の研究サイトと意識的に結ぶような戦略性のある人事も積極的に進めなければならないと思っている。これまでのように、こういう分野の研究者を国際公募しますと旗を立てて、じっと待っているだけでは駄目だ。どういう人を呼びたいのかということを主体的、戦略的に絞ることが重要だ。そのような研究者を招聘するためにも、給与などを弾力化することが不可欠だ。
世界のどういうところとつないでいくか。それには向こうから積極的につながりたいと思うようなものをこちら側が持っていないと効果がない。それをどう仕込んでいくかが鍵になる。政府が提示する公募型の事業に落とし込むだけでは十分ではない。理研の資源を活用して、理研が主体的判断で進めていくことも必要だ。国の投資資金を有効に使っていくという意味でも理研の機能は重要だ。国の公募事業も、最初から施策メニューが全てピン留めされているようなやり方だけでは良くない。提案者が自らの発想で、日本発の価値創造を世界に提示するためのやり方を考え、それを提案できるようなスキームを整えていきたい。
インタビューは2023年7月25日、埼玉県和光市の理化学研究所にて実施
聞き手:樋口 義広 JST参事役(当時)
(編集:大家 俊夫 JST・SPAP編集長)
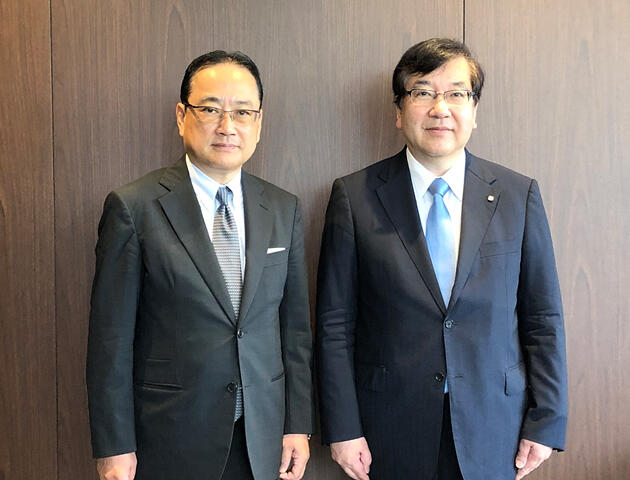
理研の五神真理事長(右)樋口義広氏

五神 真(ごのかみ まこと):
国立研究開発法人 理化学研究所理事長
1957年東京都生まれ。私立武蔵高校卒、東京大学理学部物理学科卒。米国AT&Tベル研究所客員研究員、科学技術振興事業団(現・科学技術振興機構)創造科学推進事業「五神協同励起プロジェクト」の総括責任者などを経て、98年東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻教授、2015年東京大学総長(第30代)に。22年理化学研究所理事長に就任。
<理研概略>
日本で唯一の自然科学の総合研究所として、物理学、工学、化学、数理・情報科学、計算科学、生物学、医科学などに及ぶ広い分野で研究を推進。1917年に財団法人として創設。戦後、株式会社科学研究所、特殊法人時代を経て、2003年文部科学省所轄の独立行政法人理化学研究所として再発足し、15年国立研究開発法人理化学研究所に。研究成果を社会に普及させるため、大学や企業との連携による共同研究、受託研究等を実施しているほか、知的財産等の産業界への技術移転を積極的に進めている。
理研ホームページ: https://www.riken.jp/
【国際頭脳循環の重要性と日本の取り組み】
国際頭脳循環の強化は、活力ある研究開発のための必須条件である。日本としても、グローバルな「知」の交流促進を図り、研究・イノベーション力を強化する必要があるが、そのためには、研究環境の国際化を進めるとともに、国際人材交流を推進し、国際的な頭脳循環のネットワークに日本がしっかり組み込まれていくことが重要である。
本特集では、関係者へのインタビューを通じて、卓越した研究成果を創出するための国際頭脳循環の促進に向けた日本の研究現場における取り組みの現状と課題を紹介するとともに、グローバル研究者を引きつけるための鍵となる日本の研究環境の魅力等を発信していく。